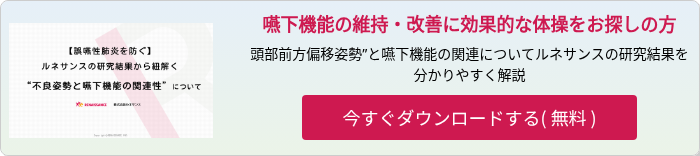個別機能訓練加算の基本ガイド。算定要件とⅠ・Ⅱの違いも解説【2024年度改正対応】

介護事業者やデイサービスなどの通所リハビリテーション施設では、収益向上の方法として、個別機能訓練加算の取得に取組んでいるケースも少なくありません。
しかし、算定要件やサービス内容による取得単位数の違いなど、加算取得の仕組みが複雑といった課題もあります。
これから個別機能訓練加算の取得を検討している事業者の方は、基本的な仕組みや算定要件について理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、個別機能訓練加算の基本概要と算定要件を解説します。
この記事を読んでいるあなたに、次におすすめのお役立ち情報はこちら
- お役立ち記事|個別機能訓練計画書の書き方と作成のコツを解説
個別機能訓練加算とは
個別機能訓練加算とは、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームなどの所定の介護施設において、利用者に対して個別の機能訓練を実施した場合に算定できる加算です。利用者一人ひとりの心身状態や生活機能に合わせた訓練計画を策定し、それに基づいた機能訓練を提供することで、自立支援・重度化防止を図ることを目的としています。この加算には「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ」と「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ」の2種類があり、主に機能訓練指導員の配置人数によって区分されています。
さらに、LIFEデータ提出に関する「個別機能訓練加算(Ⅱ)」も存在します。
詳しくはこちらの記事でご紹介しています。あわせてご確認ください。
個別機能訓練加算のメリット
個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ)の導入は、利用者の生活の質向上だけでなく、職員のスキルアップや業務効率化を通じて事業所の経営改善にもつながります。LIFEとの連携によるデータ活用で、サービスの質向上と収益増加を両立できる点が大きな特徴です。
① 利用者のQOL(生活の質)の向上
個々の身体状況や生活ニーズに即した訓練を実施することで、身体機能の改善や日常生活動作(ADL)への自立支援が期待できます。結果として、利用者満足度の向上や施設の評価アップにもつながります。
ADL維持加算についてはこちら。
② 職員のスキル強化と定着促進
計画立案や評価を通じて職員の専門性が向上し、利用者の変化を実感することでモチベーションアップ。加算要件対応の記録業務もスキルアップに寄与し、職員定着率向上にもつながります。
③ 事業所の安定経営と質の向上
加算算定による収益増加は設備投資や研修、待遇改善に充てられ、人材採用・定着を支えます。さらに、『R-Smart』を活用すれば帳票作成やLIFE連携が効率化され、加算算定率の向上と業務負担の軽減が期待できます。これによりサービスの質が高まり、利用者満足の好循環を生み出します。
詳しくはこちら。
④ 計画的かつ質の高いサービス運営
PDCAサイクルを取り入れた計画的な訓練運営と、LIFE連携による提出業務の効率化・データ分析で、根拠に基づくサービス改善が可能。加算算定率の向上にも直結します。
個別機能訓練加算の算定要件
2021年度に行われた介護報酬改定で算定要件や取得単位数などが見直されており、より充実したサービスの提供が進められています。
介護報酬改定では、改定前の個別機能訓練加算ⅠとⅡが統合されて、個別機能訓練加算Ⅰとしてまとめられています。改定後の個別機能訓練加算Ⅰはイとロに分けられ、算定要件や取得単位数の一部に違いがあります。
ここでは、算定要件を項目別で詳しく解説します。
①取得単位数
個別機能訓練加算Ⅰ:イ | 1日につき56単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ:ロ | 1日につき76単位 |
イとロでは、それぞれ単位数に違いがあるため、加算取得を検討する場合は注意が必要です。また、イとロは併用して算定することはできません。
イとロの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
②人員配置
▼機能訓練指導員
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 鍼灸師(一定の実務経験が必要を有する者)
イの場合は配置時間の定めがないため、短時間労働者でも問題ありません。一方、ロの場合も令和6年度の介護報酬改定により、配置時間の定めはありません。
詳しくは、厚生労働省「6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」をご参照ください。
③作成・提出が必要な書類
作成書類 | 概要 |
個別機能訓練計画書 | 利用者の状況・ニーズを把握する書類 |
興味関心チェックシート | 利用者のADL(日常生活動作)・IADL(手段的日常生活動作)の状況を記載する書類 |
生活機能チェックシート | 機能訓練の目標やプログラムなどを記載する書類 |
イとロは、ともに個別機能訓練計画書の作成が要件です。
事業所の職員が利用者の居宅自宅を訪問して、ニーズの把握や生活状況の確認やニーズの把握などを行ったうえで、個別機能訓練計画書を作成します。
また、個別機能訓練計画の作成にあたって、興味関心チェックシートと生活機能チェックシートの作成も必要です。
また、こちらの記事では、個別機能訓練計画書の書き方と効率的に作成するコツを 解説しています。あわせてご覧ください。
④機能訓練項目
イとロは、利用者の心身状況に合わせた機能訓練項目を柔軟に設定します。項目を設定する場合は、身体機能と生活機能の向上を意識することが大切です。
また、複数の項目を準備した場合は、利用者の生活意欲が増進されるように選択します。
訓練時間については決まりがないため、機能訓練項目の実施に必要な1回当たりの訓練時間を考慮して、適切に設定します。
⑤対象者・実施者
訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団、もしくは個別 |
訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接訓練を実施 |
イとロの対象は、どちらも5人程度以下の小集団、または個別の利用者です。個別機能訓練計画の内容に沿って、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した利用者を小集団として実施します。
⑥進捗状況の評価
イとロは、進捗状況の評価を3ヶ月に1回以上の割合で実施します。
評価の際は、利用者の自宅を訪問し生活状況を確認したうえで、利用者またはその家族に個別機能訓練計画の進捗状況を説明します。評価の結果、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しが必要です。
なお、加算算定の仕組みや、PDCAサイクルに必要な科学的介護情報システム(以下、LIFE)についてはこちらで詳しく解説しています。
併せてこちらもご覧ください。
個別機能訓練加算ⅠとⅡの違い
これまで解説した個別機能訓練加算Ⅰとは別に個別機能訓練加算Ⅱがあります。Ⅱは2021年度の介護報酬改定で新設されており、Ⅰに上乗せして算定します。個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いは、LIFEを活用したデータ提出の有無です。
個別機能訓練加算Ⅱを算定する際は、個別機能訓練加算Ⅰの算定要件を満たすことに加えて、個別機能訓練計画書の内容をLIFEに提出して、フィードバックを受ける必要があります。
フィードバックを受けたら、利用者に合わせた計画の見直しや改善を行います。
個別機能訓練加算(Ⅱ) | |
|---|---|
単位数 | 20単位/月(Ⅰ)に上乗せして算定 |
対象者 | 要介護、個別機能訓練加算Ⅰの算定要件を満たしている者 |
算定要件 |
|
まとめ
この記事では、個別機能訓練加算について以下の内容で解説しました。
- 個別機能訓練加算とは
- 個別機能訓練加算の算定要件
- 個別機能訓練加算ⅠとⅡの違い
個別機能訓練加算は2021年度介護報酬改定により、新たな要件でサービスの質の向上を目指せるようになりました。
しかし、個別機能訓練加算Ⅰの要件は一部相違する部分があるため、加算取得を検討する際は注意が必要です。
また、個別機能訓練加算Ⅰの取組みに加えて、LIFEへデータを提出することで、個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たすことができます。
個別機能訓練換算計画書の書き方については以下の記事で解説しています。ぜひ こちらをご覧ください。
『 ルネサンス』が提供する加算取得支援サポートサービス『 R-Smart』は、帳票作成やLIFEとの連携などを徹底サポートして、担当者の業務効率化に貢献します。
R-Smartのサービスに関するご質問や資料請求などのお問い合わせは、 こちらをご確認ください。