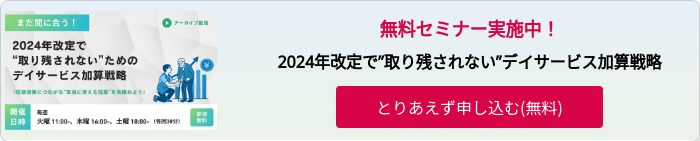個別機能訓練加算 イとロの違いを徹底解説【2024年度改定対応】

個別機能訓練加算はデイサービスなどの介護施設において重要な加算制度ですが、「イ」と「ロ」の区分があり、それぞれの違いや算定要件を理解することが事業所運営の鍵となります。特に2024年度の介護報酬改定により、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数や人員配置要件に変更が加えられました。本記事では個別機能訓練加算のイとロの違いを中心に、2024年度改定の詳細や算定のポイントまで解説します。
その他、この記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 | 個別機能訓練計画書の書き方と作成のコツを解説
- お役立ち記事 | 個別機能訓練加算の基本と算定要件を解説
目次[非表示]
- 1.個別機能訓練加算とは
- 1.1.対象サービス
- 2.個別機能訓練加算 イとロの違い【2024年度改定対応】
- 2.1.個別機能訓練加算(Ⅰ)イの特徴
- 2.2.個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの特徴
- 2.3. 2024年度改定による変更点
- 2.4.イとロの選択ポイント
- 3.個別機能訓練加算(Ⅱ)とは
- 4.個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
- 5.個別機能訓練加算 イとロの算定要件の詳細
- 6.個別機能訓練加算 イとロの算定に必要な書類
- 6.1.自治体への届出書類
- 6.2.利用者ごとに作成する書類
- 7.個別機能訓練加算 イとロの算定の流れ
- 7.1.人員配置の確認・整備
- 7.2.自治体への届出
- 7.3.居宅訪問・アセスメント
- 7.4.個別機能訓練
- 7.5.機能訓練の実施
- 7.6.評価と計画の見直し
- 8.個別機能訓練加算 イとロの違いと選択のポイント
- 8.1.イとロの主な違い(2024年度改定後)
- 8.2.事業所に合った選択をするポイント
- 8.3.2024年度改定のメリット
- 9.個別機能訓練計画書作成のポイント
- 10.FAQ(よくある質問)
- 11.まとめ
個別機能訓練加算とは
個別機能訓練加算は、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームなどの所定の介護施設において、利用者に対して個別の機能訓練を実施した場合に算定できる加算です。利用者一人ひとりの心身状態や生活機能に合わせた訓練計画を策定し、それに基づいた機能訓練を提供することで、自立支援・重度化防止を図ることを目的としています。
この加算には「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ」と「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ」の2種類があり、主に機能訓練指導員の配置人数によって区分されています。さらに、LIFEデータ提出に関する「個別機能訓練加算(Ⅱ)」も存在します。
対象サービス
個別機能訓練加算が算定できる主な介護サービスは以下の通りです。
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護
- 特別養護老人ホーム
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型通所介護
個別機能訓練加算 イとロの違い【2024年度改定対応】
個別機能訓練加算(Ⅰ)のイとロの違いを詳しく解説します。2024年度の介護報酬改定により、特に「ロ」の条件に大きな変更がありました。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの特徴
- 単位数:56単位/日
- 機能訓練指導員の配置:専従1名以上(配置時間の定めなし)
-
算定要件:
- 居宅訪問によるニーズと生活状況の把握
- 多職種協働での個別機能訓練計画作成
- 個別または5人程度以下の小集団での機能訓練
- 機能訓練指導員による直接実施
- 身体機能及び生活機能向上を目的とした訓練項目の設定
- 3ヶ月ごとの評価と計画見直し
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの特徴
- 単位数:76単位/日(2024年度改定前は85単位/日)
- 機能訓練指導員の配置:専従2名以上(2024年度改定により配置時間の定めなしに変更)
-
算定要件:
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件をすべて満たすこと
- イの機能訓練指導員1名に加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上追加配置すること
2024年度改定による変更点
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに関して、2024年度の介護報酬改定で以下の変更がありました。
-
単位数の引き下げ
- 改定前:85単位/日
- 改定後:76単位/日
-
機能訓練指導員の配置要件の緩和
- 改定前:イに加えて専従1名以上(サービス提供時間を通じて配置)
- 改定後:イに加えて専従1名以上(配置時間の定めなし)
この変更により、機能訓練指導員の配置がより柔軟になり、限られた人材を効率的に活用できるようになりました。
イとロの選択ポイント
事業所の状況に応じて、イとロのどちらを算定するか検討する際のポイントは以下の通りです。
-
人員体制
- 機能訓練指導員を2名以上確保できる場合は「ロ」
- 1名のみの場合は「イ」
-
収益性
- ロの方が単位数は高いが、人件費の増加も考慮する必要あり
- 利用者数と加算単位数のバランスを考慮
-
柔軟な運用
- 機能訓練指導員が1名しか確保できない日がある場合は、その日のみ「イ」に切り替えて算定可能
- このような運用をする場合は、利用者に事前に説明が必要
個別機能訓練加算(Ⅱ)とは
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、2021年度の介護報酬改定で新設された加算で、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバック活用を要件としています。
- 単位数:20単位/日
- 算定要件:
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロを算定していること(上乗せ加算)
- 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報をLIFEにデータ提出すること
- LIFEからのフィードバック情報を活用してPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ること
個別機能訓練加算(Ⅱ)は単独での算定はできず、必ず個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロと同時算定する必要があります。個別機能訓練加算(Ⅰ)で提供した機能訓練の内容をLIFEに提出し、そのフィードバックを活用することで科学的根拠に基づく介護(科学的介護)を推進するための加算です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の大きな違いはLIFEを活用したデータ提出の有無です。
個別機能訓練加算(Ⅰ):利用者の状態を評価し、個別の機能訓練計画を作成・ 実施した場合に算定できます。令和3年度改定以降は、さらに「イ」と「ロ」に 区分され、配置要件や算定条件が異なります。
個別機能訓練加算(Ⅱ):(Ⅰ)の要件に加え、LIFEへの情報提出と フィードバックを活用し、科学的根拠に基づいた機能訓練を行う場合に算定できます。
また、個別機能訓練加算IとⅡの違いについてはこちらの記事でも解説しています。合わせてご確認ください。
個別機能訓練加算 イとロの算定要件の詳細
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロに共通する算定要件と、それぞれに特有の要件について詳しく解説します。
共通の算定要件
- 居宅訪問とニーズ把握
- 利用者の居宅を訪問し、ニーズと生活状況を把握
- 生活機能チェックシートによる評価が必須
- 興味・関心チェックシートの活用も推奨
- 多職種協働による計画作成
- ケアプランと整合性のある個別機能訓練計画の作成
- 心身状況に応じた具体的な目標設定
- 身体機能および生活機能の向上を目的とする訓練項目の設定
- 訓練の実施方法
- 類似の目標・訓練項目を持つ5人程度以下の小集団または個別対応
- 機能訓練指導員による直接実施
- おおむね週1回以上の訓練実施
- 評価と見直し
- 3ヶ月に1回以上の居宅訪問による評価
- 居宅での生活状況の確認
- 必要に応じた計画の見直し
- 利用者・家族への説明とケアマネージャーへの報告
イとロの主な違い
両者の主な違いは「機能訓練指導員の配置人数」と「算定単位数」です。
区分 | 単位数 | 機能訓練指導員の配置 |
|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 専従1名以上(配置時間の定めなし) |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | 専従2名以上(配置時間の定めなし) |
個別機能訓練加算 イとロの算定に必要な書類
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロを算定するには、共通の書類が必要です。書類作成と管理が加算算定の重要なポイントとなります。
自治体への届出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表
- 機能訓練指導員の資格証(写し)
※届出書類は自治体ごとに若干異なる場合がありますので、管轄自治体に確認しましょう。
利用者ごとに作成する書類
①生活機能チェックシート(必須)
生活機能チェックシートは、利用者の居宅における生活機能を評価するための書類です。個別機能訓練加算の算定において必須の書類となります。
- 主な評価項目
- ADL(日常生活動作):食事、排泄、入浴など
- IADL(手段的日常生活動作):調理、洗濯、買い物など
- 基本動作:立ち上がり、歩行、階段昇降など
- 評価方法
項目ごとに「自立」「見守り」「一部介助」「全介助」などで評価
生活課題の有無を記入
作成タイミング
初回居宅訪問時
3ヶ月ごとの評価時
②興味・関心チェックシート(任意だが推奨)
興味・関心チェックシートは、利用者の日常生活や社会参加における興味・関心事を把握するためのツールです。厚生労働省は個別機能訓練計画書作成時に活用を推奨しています。
- 評価項目
- 日常の活動(料理、園芸、読書など)
- 社会活動(ボランティア、地域活動など)
- 趣味や特技
- 評価方法
- 「している」「してみたい」「興味がある」の3つの観点でチェック
③個別機能訓練計画書
個別機能訓練計画書は、利用者ごとに作成する訓練計画書です。生活機能チェックシートと興味・関心チェックシートの結果を踏まえ、多職種協働で作成します。イとロどちらの加算を算定する場合も、同じ様式の計画書を使用します。
- 主な構成項目
- 利用者の基本情報
- 身体状況・社会参加の状況
- 健康状態(疾患・投薬情報等)
- 長期目標・短期目標
- 訓練項目(内容・頻度・時間等)
- 作成・更新頻度
- 初回作成:サービス開始前
- 更新:3ヶ月に1回以上
④実施記録
個別機能訓練を実施した際の記録です。イとロどちらの加算を算定する場合も、同様の記録が必要です。
- 記録内容
- 実施日時(例:10:00~10:20)※時間帯を明記
- 訓練内容
- 担当者名
- 記録頻度
- 訓練実施のたびに記録
個別機能訓練加算 イとロの算定の流れ
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定手続きの流れは基本的に同じです。どちらを算定する場合も、以下のステップに沿って進めます。
人員配置の確認・整備
まず、算定要件を満たす人員配置が可能かを確認します。
- イを算定する場合: 専従の機能訓練指導員1名以上を確保
- ロを算定する場合: 専従の機能訓練指導員2名以上を確保
機能訓練指導員として認められる資格は以下の通りです。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護師・准看護師
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 一定の実務経験を有するはり師・きゅう師
自治体への届出
算定に必要な届出書類を準備し、管轄の自治体に提出します。届出書類の受理をもって算定が可能になります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表
- 機能訓練指導員の資格証(写し)
同時に、ケアマネージャーや利用者に対して個別機能訓練加算の算定について説明します。
居宅訪問・アセスメント
利用者の居宅を訪問し、生活環境や日常生活の状況、ニーズを把握します。
- 生活機能チェックシートの作成: ADL・IADL・基本動作の状況を評価
- 興味関心チェックシートの活用: 利用者の趣味や好みなどを把握
- 環境評価: 自宅の段差や動線など環境面のチェック
- ニーズの確認: 本人・家族の希望や課題の把握
この居宅訪問は、機能訓練指導員以外の職種が行うことも可能です。
個別機能訓練
居宅訪問で得た情報をもとに、多職種協働で個別機能訓練計画書を作成します。
- 利用者の基本情報や疾患・投薬情報などを記載
- 長期目標と短期目標を設定
- 具体的な訓練項目と頻度・時間を設定
- 本人・家族への説明と同意を得る
- ケアマネージャーへの報告
イとロのどちらを算定する場合も、作成する計画書の内容や様式は同じです。
機能訓練の実施
計画に基づいて機能訓練を実施します。イとロのどちらを算定する場合も、実施方法は基本的に同じです。
- 類似の目標を持つ5人程度以下の小集団または個別で実施
- 機能訓練指導員が直接実施
- おおむね週1回以上の頻度で実施
- 実施記録を作成(実施時間・内容・担当者などを記録)
実施時は単に身体機能の向上だけでなく、生活機能の維持・向上につながるよう実践的な訓練を心がけます。
評価と計画の見直し
3ヶ月に1回以上、以下のプロセスで評価と計画の見直しを行います。
- 利用者の居宅を訪問し、生活状況の変化を確認
- 個別機能訓練の効果を評価
- 必要に応じて目標や訓練内容を見直し
- 本人・家族への説明
- ケアマネージャーへの報告
初回同様、評価のための居宅訪問は機能訓練指導員以外の職種が実施することも可能です。
個別機能訓練加算 イとロの違いと選択のポイント
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの主な違いは「機能訓練指導員の配置人数」と「算定単位数」です。2024年度の介護報酬改定により、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件が緩和され、単位数も見直されました。
イとロの主な違い(2024年度改定後)
区分 | 単位数 | 機能訓練指導員の配置 |
|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 専従1名以上(配置時間の定めなし) |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | 専従2名以上(配置時間の定めなし) |
事業所に合った選択をするポイント
-
機能訓練指導員の確保状況
機能訓練指導員を1名しか確保できない場合は「イ」
機能訓練指導員を2名以上確保できる場合は「ロ」
-
柔軟な運用方法
ロを基本としつつも、機能訓練指導員が1名しか確保できない日は「イ」に切り替え可能
この場合、利用者に営業日ごとの配置体制を事前に説明することが必要
-
収益性のバランス
ロの方が単位数は高いが、機能訓練指導員の人件費増加も考慮
利用者数と人件費のバランスを考えた選択が重要
2024年度改定のメリット
今回の改定により、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの配置時間の定めがなくなったことで、以下のようなメリットが生じています。
- 機能訓練指導員の柔軟な配置が可能に
- 訓練の時間帯に合わせた効率的な人員配置ができる
- 限られた専門職の有効活用が図れる
個別機能訓練加算はリハビリテーション職など専門職の配置が必要となる加算ですが、適切に運用することで利用者の生活機能向上と事業所の収益向上の両方につなげることができます。自分の事業所の状況に合わせて、イとロのどちらが適しているか検討し、効果的な個別機能訓練を提供しましょう。言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師など。
-
自治体への届出
- 必要書類の準備・提出
- ケアマネージャーや利用者への説明
-
書類作成と訓練実施
居宅訪問によるアセスメント
生活機能チェックシート・興味・関心チェックシートの作成
個別機能訓練計画書の作成
利用者・家族への説明と同意
計画に基づいた訓練の実施
実施記録の作成
-
評価と計画の見直し
3ヶ月に1回以上の居宅訪問
生活状況の確認と評価
必要に応じた計画の見直し
利用者・家族への説明
ケアマネージャーへの報告
個別機能訓練計画書作成のポイント
長期目標の設定
長期目標は、単に身体機能の向上だけでなく、具体的な生活上の行為の達成を含めた目標設定が重要です。以下の3つの視点から目標を設定します。
- 心身機能:筋力、耐久性、関節可動域など
- 活動:歩行、食事、入浴など
-
参加:買い物、外出、社会交流など
例えば「スーパーマーケットに食材を買いに行く」「家族と散歩を楽しむ」など、生活の質の向上が実感できる具体的な目標を設定します。
短期目標の設定
短期目標は、長期目標を達成するために必要な行為を細分化したものです。長期目標が「スーパーマーケットに食材を買いに行く」の場合、短期目標としては以下のようなものが考えられます。
- 下肢筋力・耐久性の向上
- スーパーマーケットまで歩いて行ける
- 家族と家の周りの散歩を楽しめる
訓練項目の設定
訓練項目は、短期目標の達成に必要なプログラムです。利用者の心身状況に応じて複数の訓練項目を準備し、生活意欲が増進されるよう援助することが大切です。
例えば、「スーパーマーケットに行く」という目標に対しては
- 下肢筋力強化訓練
- 歩行訓練
- 段差昇降の訓練
- 買い物の訓練
など、具体的で実践的な訓練項目を設定します。
FAQ(よくある質問)
Q1:個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロは併算定できますか?
A:いいえ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロは併算定できません。事業所の機能訓練指導員の配置状況に応じて、いずれかを選択して算定します。
Q2:通常2名の機能訓練指導員を配置し、ロを算定している場合、職員の休みなどで1名体制になる日はどうすればよいですか?
A:機能訓練指導員が1名しか確保できない日がある場合は、その日のみ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することが可能です。ただし、このような運用をする場合は、営業日ごとの機能訓練指導員の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要があります。
Q3:2024年度の改定で個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件はどのように変わりましたか?
A:2024年度の改定前は、イに加えて「サービス提供時間を通じて専従1名以上」という配置時間の定めがありましたが、改定後は「イに加えて専従1名以上(配置時間の定めなし)」となりました。つまり、サービス提供時間全体を通じての配置が不要となり、機能訓練を行う時間帯に合わせた柔軟な配置が可能になりました。
Q4:看護師が機能訓練指導員を兼務することは可能ですか?
A:可能です。ただし、機能訓練指導員として従事している間は、看護師としての業務はできません。また、看護職員が個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事する場合は、看護職員としての人員基準の算定には含めることができない点に注意が必要です。
Q5:機能訓練指導員として認められる資格は何ですか?
A:以下の資格が機能訓練指導員として認められています。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護師・准看護師
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 一定の実務経験を有するはり師・きゅう師
Q6:個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのどちらと算定できますか?
A:個別機能訓練加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのどちらとも算定可能です。個別機能訓練加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していることが前提の上乗せ加算となります。つまり、(Ⅰ)イまたは(Ⅰ)ロのいずれかを算定していれば、(Ⅱ)も算定できます。
Q7:居宅訪問は必ず機能訓練指導員が行う必要がありますか?
A:いいえ、居宅訪問は機能訓練指導員に限らず、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、介護職員・生活相談員・看護職員等、どの職種でも問題ありません。また、3ヶ月ごとの評価のための居宅訪問も、毎回同一人物が行う必要はありません。
Q8:個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定において、訓練の実施頻度はどの程度必要ですか?
A:個別機能訓練計画に定めた訓練項目を実施するために必要な1回あたりの訓練時間を適切に設定し、おおむね週に1回以上を目安に実施することが求められています。なお、訓練時間は「20分」というような抽象的な記載ではなく、「10:00~10:20」というように具体的な時間帯を記録することが必要です。
Q9:イとロで訓練内容や対象者に違いはありますか?
A:いいえ、訓練内容や対象者に違いはありません。イとロの違いは機能訓練指導員の配置人数と算定単位数のみです。どちらの場合も、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団、または個別対応で機能訓練を実施します。
Q10:2024年度改定で個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数はなぜ引き下げられたのですか?
A:個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数引き下げは、機能訓練指導員の配置要件の緩和とセットで行われました。配置時間の定めがなくなったことで人員配置が柔軟になり、限られた人材の有効活用が図れるようになった一方で、サービス提供時間全体を通じての配置が不要になったことから、単位数も適正化されたと考えられます。
Q11:個別機能訓練計画書の更新頻度はどのくらいですか?
A:個別機能訓練計画書は3ヶ月に1回以上の頻度で更新する必要があります。更新の際は、居宅訪問により利用者の生活状況を確認し、訓練の効果を評価した上で、必要に応じて目標や訓練内容を見直します。
まとめ
個別機能訓練加算は、利用者の自立支援・重度化防止に大きく貢献する重要な加算です。2024年度の介護報酬改定では、機能訓練指導員の配置要件の緩和と単位数の見直しが行われ、より柔軟な運用が可能になりました。
適切な算定のためには、正確な書類作成と定期的な評価が不可欠です。利用者一人ひとりの生活状況やニーズを把握し、効果的な機能訓練を提供することで、利用者のQOL向上と事業所の安定経営の両立を目指しましょう。
イとロの違いを理解することは第一歩に過ぎません。算定の実務や書類作成には、さらに多くのポイントがあります。
加算制度全体像をつかみたい方におすすめのお役立ち記事はこちら。
計画書の書き方でお悩みの方におすすめのお役立ち記事はこちら。
また、より実践的な内容を学びたい方におすすめのウェビナー(無料)はこちら。
制度を正しく理解し、事業所に合った運用方法を見つけましょう。
『ルネサンス』では、口腔・運動器・レッドコートに関する映像プログラムを提供しています。直営店舗の検証において運動前後での変化も実証済みのため、安心してご利用いただけます。お気軽にお問合せください。