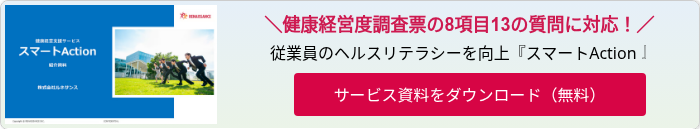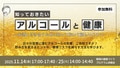健康経営を推進するためのイベント企画ガイド|効果的な施策と継続のコツを徹底解説

その他、この記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 | 健康経営に役立つサービスと選び方!ルネサンスのおすすめサービス10選
- お役立ち記事 | 健康経営の推進で期待できる効果と6つの取組み事例を紹介
なぜ今、健康経営に「イベント」が求められているのか?
健康経営の実現におけるイベントの役割
健康経営は従業員の健康を組織の成長と結びつける戦略的取り組みです。
中でもイベントは、健康行動の「見える化」と「巻き込み」を同時に実現できる手段として注目されています。
- 部署間の垣根を越えたコミュニケーションが生まれる
- 健康行動が“社内の話題”になり、行動変容を後押し
- 健康文化の醸成に直結する
単なる福利厚生にとどまらず、組織全体の生産性や心理的安全性にも寄与します。
企業と従業員双方にとってのメリット
- 企業側のメリット:生産性向上、医療費削減、離職率低下、組織エンゲージメント強化
- 従業員側のメリット:健康への意識向上、仲間意識・安心感、職場満足度アップ
イベントを通じた社内コミュニケーションの活性化は、心理的安全性や連帯感の向上にも貢献します。
多くの企業が実践する!効果的な健康経営イベントの取り組み例
歩数チャレンジ型イベントで運動習慣を促進
歩数チャレンジはスマホアプリやウェアラブル端末を活用して運動習慣を促進する定番施策です。「日常の中に運動を取り入れるきっかけ」として人気です。
- 個人やチームでランキング化し、ゲーム感覚で継続
- 運動習慣のない層にも自然な行動変容を促す
- 部署対抗戦や表彰制度を組み合わせると社内が活気づく
オンライン講座で健康リテラシーを底上げ
オンライン健康講座は、時間や場所にとらわれず幅広い層に情報を届けられる施策です。
- 睡眠・栄養・運動・メンタルヘルスなど、テーマを月替わりで実施
- 医師や専門家の講座で「正しい知識」に基づく行動変容を後押し
- ライブ配信+アーカイブで、参加ハードルを低減
データを活用したKPI設計と効果測定
イベントの効果を可視化するには、定量+定性の両面評価が欠かせません。
- 参加率・継続率・満足度
- 健康診断・ストレスチェック等の指標との変化比較
- アンケートや自由記述で改善ポイントを抽出
データを活用することで改善ポイントが明確になり、経営層への説明や次回施策への説得力も高まります。
健康経営イベントの企画・実施ステップ
目的と課題の明確化
イベントを成功させるには、「なぜ実施するのか」 「何を変えたいのか」という目的と課題の明確化が不可欠です。
- 現状の健康課題・ニーズ(運動不足・睡眠・メンタルなど)の洗い出し
- 従業員アンケートで関心のあるテーマを把握
- KPIの設定(例:参加率、行動変容率)
現状の健康課題や組織ニーズを把握し、従業員の行動変容につながる狙いを具体的に設定することで、効果的なイベント設計が可能となります。
イベント形式の選定(オンライン・オフライン)
イベントは目的や対象に応じて、開催形式を選択しましょう。
- オフィス対面型/リモート型/ハイブリッド型を目的に応じて選択
- 支店・在宅勤務者にも配慮した形式は参加率向上に直結
対象者に合わせた柔軟な形式設計は、参加のハードルを下げ、全社的な取り組みとしての一体感を生み出します。
企画立案〜社内告知〜実施〜振り返りの流れ
イベントは「企画→社内告知→実施→振り返り」という流れで進行します。丁寧な告知で関心を高め、実施後はアンケートや定量データをもとに振り返りを行いましょう。
- 企画立案:テーマ、実施方法、KPIを決定
- 社内告知:メール、掲示板、Teams/Slackなど複数チャネルで告知
- 実施:当日の運営をシンプル化し、体験価値を重視
- 振り返り:アンケートとデータで改善点を抽出し次回施策へ
このプロセスを継続することで、改善点を反映した次回施策につながります。
従業員の参加率を高めるための工夫
ゲーム性の導入(ランキング・表彰制度など)
単なる参加型から「参加したくなる」仕組みへと進化させるには、ゲーム性の導入が効果的です。ランキングやチーム対抗、表彰制度を設けることで、自然と競争心や協力意識が生まれます。職場の交流促進にもつながり、健康行動を楽しく継続しやすくなります。
インセンティブや福利厚生との連動
ポイント付与や景品制度、カフェチケットや特別休暇といったインセンティブとの連動は、参加率を押し上げる大きな要素です。また、社内の福利厚生制度との接続(例:健康ポイントの付与)により、イベントが一過性に終わらず、日常生活の一部として定着します。
柔軟な参加形式の設計(リモート対応など)
多様な働き方が広がる今、イベントも柔軟性が求められます。フレックスや在宅勤務の従業員でも参加できるよう、オンデマンド形式や複数時間帯開催、アーカイブ視聴の仕組みを取り入れましょう。「いつでも・どこでも」参加できる環境整備が鍵となります。
イベント実施後の効果測定と次回施策への活用
アンケート結果と行動変化の可視化
イベント実施後には、満足度や学び、行動変化などを把握するアンケートを実施し、参加者の声を反映させることが重要です。定量評価に加え、自由記述を通じた定性分析も、次回施策の方向性を検討するうえで大きなヒントとなります。
健康指標や従業員満足度の変化確認
イベントを通じた健康意識の変化は、ストレスチェックや健診結果、アンケート等の数値に表れます。さらに、職場の活性度や従業員満足度との関連性にも着目し、健康経営が組織全体にどのような影響を与えているかを可視化することが求められます。
報告資料作成のポイントと事例共有の重要性
施策効果を社内外に伝えるには、参加率・満足度・成果などを簡潔にまとめた報告書が有効です。グラフやコメントを交えてわかりやすく整理し、他部署や他社の事例と比較共有することで、健康経営の推進が組織全体に広がっていきます。
イベント企画Q&A
Q.健康経営イベントはどのくらいの頻度で実施すべきですか?
A.理想は年数回の大型イベントと月1回のライトな取り組みの併用です。頻度よりも“継続性”と“多様性”を意識し、従業員の関心や行動変容を引き出すことを重視しましょう。短時間でも、定期的な接点を設けることで健康習慣の定着を図れます。
Q.小規模な企業でもイベントは導入できますか?
A.はい、可能です。リソースが限られていても、オンライン講座や社内掲示板の活用、ランチタイムセミナーなど、負担の少ない形式から始められます。自治体や保険者、外部専門機関との連携を活用することで、導入のハードルは一層下がります。
Q.イベントの効果を数値でどう測ればいいですか?
A.参加率・継続率・満足度・行動変化・健康指標(歩数・睡眠・ストレスチェック等)の前後比較等が基本です。実施前に評価項目(KPI)を設けておくことで、定量的に振り返りがしやすく、次回施策に向けた改善も具体的になります。
Q.参加率が低いとき、どう改善すればよいでしょうか?
A.関心が低い理由を把握することが第一です。参加者の声よりも、イベントに「参加しない人の理由」を確認することが何よりも大切です。テーマ設定、時間帯、告知方法、参加手段などを見直し、従業員の声を反映した改善を行いましょう。また、上司からの声かけやチーム参加の仕掛けなど、周囲からの巻き込みも効果的です。
まとめ|改めて、考える。健康経営イベントの目的とは
押さえておきたい大切な視点:健康的な組織風土の醸成
健康イベントを効果的に機能させるには、単発の施策としてではなく、組織に根づいた支援文化との連動が欠かせません。特に重要なのがPOS(Perceived Organizational Support:知覚化された組織支援)とのつながりです。従業員が「自分は組織に大切にされている」と感じられる環境では、健康に関心が薄い人でも、周囲の声かけや参加の誘いを素直に受け入れやすくなります。こうした支援の文化が形式知として共有されていることが、イベントの成功と継続の鍵となります。
また、こちらの記事では従業員の健康意識を増進させる企業の取り組み事例をご紹介しています。あわせてご確認ください。
また、こちらの記事では従業員の健康意識を増進させる企業の取り組み事例をご紹介しています。あわせてご確認ください。
イベントの価値を最大化する3つの軸
健康経営イベントの価値は「参加・習慣化(継続)・文化形成」の3軸にあります。
- 参加:関わりやすい設計
- 習慣化:継続しやすい工夫
- 文化形成:組織風土として根付かせる
一人ひとりの健康行動のきっかけとなるだけでなく、組織の信頼感やつながりを育む場として位置づけ、戦略的に設計することが効果最大化のカギとなります。
継続運用のハードルを下げる工夫
企画・運営の継続には、内容のテンプレート化や外部サービスの活用が有効です。すべてを手作りしようとせず、小さく始めて試行錯誤を重ねることで無理なく運用でき、組織内でのノウハウ蓄積にもつながります。
【スマートAction】による定期開催型プログラムの活用
スマートActionは、健康診断やストレスチェックのデータと連動し、従業員の状態に応じたオンラインプログラムを提供するサービスです。定期開催・自動化された仕組みにより、企画・実行・振り返りを一気通貫で支援し、持続可能な健康経営を後押しします。
- 定期開催と自動化により担当者の負担を軽減
- データ活用で継続的な改善と説得力ある報告が可能