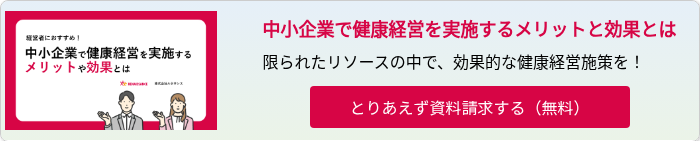ブライト500とは?中小企業が健康経営で選ばれるための認定制度を徹底解説

ブライト500とは、中小規模法人部門の認定企業の中から、特に優れた取り組みを実践する上位500社を選出する制度で、「中小企業版ホワイト500」とも呼ばれています。本記事では、
- ブライト500の位置づけ
- メリットと活用方法
- 認定基準と評価ポイント
- 認定取得のステップと申請手順
など、制度の目的やメリット・申請までの具体的な流れまで、詳しく解説しています。
この記事を読んでいるあなたにおすすめ
目次[非表示]
- 1.健康経営優良法人制度の概要と目的
- 1.1.健康経営優良法人制度とは
- 1.2.認定区分と対象法人
- 2.ブライト500の位置づけとホワイト500との違い
- 2.1.ブライト500とは
- 2.2.ホワイト500との違い
- 3.認定の背景と制度の成り立ち
- 4.ブライト500認定のメリットと活用方法
- 4.1.対外的な評価向上とブランディング
- 4.2.社内の健康意識向上と生産性改善
- 4.3.金融・自治体の優遇制度活用
- 5.ブライト500の認定基準と評価ポイント
- 5.1.必須項目と選択項目
- 5.2.ブライト500特有の評価ポイント
- 6.認定取得のステップと申請手順
- 6.1.事前準備と健康宣言事業
- 6.2.申請から認定までの流れ
- 7.認定にかかる費用と期間
- 8.ブライト500認定企業の事例と取り組み
- 9.まとめ:ブライト500を活用した健康経営の推進
健康経営優良法人制度の概要と目的
健康経営優良法人制度とは
健康経営優良法人制度とは、経済産業省と日本健康会議が策定した認定制度で、従業員の健康管理を経営的視点から捉え、戦略的に実践している法人を「見える化」することで、社会的評価を高めることを目的としています。
2025年度より、同制度の事務局運営業務は日本経済新聞社に移管され、認定審査や情報発信などの実務を担っています。
認定区分と対象法人
認定は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれ、それぞれにおいて優れた健康経営を実践する法人が選定されます。
特に中小企業では、人材確保・定着と生産性向上の観点からも注目される制度です。
ブライト500の位置づけとホワイト500との違い
ブライト500とは
ブライト500は、中小規模法人部門の認定企業の中から、特に優れた取り組みを実践する上位500社を選出する制度で、「中小企業版ホワイト500」とも呼ばれています。
ホワイト500との違い
大規模法人部門のホワイト500と並び、健康経営の先進企業としての評価を受けられる制度です。
さらに2023年度からは、挑戦途上にある企業を対象にした「ネクストブライト1000」が創設され、成長意欲のある中小企業の取り組みも評価されるようになりました。
認定の背景と制度の成り立ち
本制度は、少子高齢化・労働人口減少といった社会課題の中で、企業が従業員の健康に戦略的に向き合うことを支援する目的で2016年度に創設されました。
健康経営は、離職率の低減、職場満足度の向上、生産性の改善といった効果を通じて、企業の持続的な成長を支える経営戦略として注目されています。現在では、全国の中小企業・大企業を対象に、広く普及が進んでいます。
ブライト500認定のメリットと活用方法
ブライト500に認定されるメリットと活用方法は主に以下3つの点が挙げられます。
対外的な評価向上とブランディング
ブライト500に認定されることで、「健康を大切にする会社」として対外的な評価が高まり、採用活動や企業ブランディングに活用できます。
社内の健康意識向上と生産性改善
従業員の健康意識が高まることで生産性の向上にも寄与し、結果として経営効果も得られます。
金融・自治体の優遇制度活用
自治体や金融機関によっては、認定企業を対象に融資優遇や補助制度、入札加点の支援が設けられています。
ブライト500の認定基準と評価ポイント
必須項目と選択項目
認定は、健康診断やストレスチェックの実施、有所見者への対応といった必須項目と、運動機会の提供やメンタルヘルス支援などの選択項目を組み合わせた加点方式で評価されます。
ブライト500特有の評価ポイント
特に情報発信・地域貢献・他社への波及効果が重視され、経営トップの関与度やPDCAサイクルの運用も重要なポイントです。
認定取得のステップと申請手順
事前準備と健康宣言事業
まずは健康保険組合や自治体が推進する「健康宣言事業」に参加し、取り組み体制を整えます。
申請から認定までの流れ
- 日本経済新聞社が運営する「ACTION!健康経営ポータル」でID取得
- 指定フォーマットに従って申請書類を作成・提出
- 提出後、書類審査を経て、翌年3月に認定結果通知
不認定となった場合も、フィードバックをもとに翌年の改善につなげることが可能です。
認定にかかる費用と期間
申請費用
中小規模法人部門は15,000円(税込16,500円)、大規模法人部門は80,000円(税込88,000円)。申請後に請求書が届き、期日までに振込を行う形式です。
スケジュール目安
申請~認定通知まで約5~6か月。準備期間を含めると年単位のスケジュール設計が望まれます。更新は年ごとに行われ、継続改善が求められます。
ブライト500認定企業の事例と取り組み
事例① 運輸業×地域密着の健康支援型モデル
中堅運輸業のA社では、社内に管理栄養士と保健師を配置し、従業員の日々の食生活や睡眠習慣の改善に取り組んでいます。毎朝の健康朝礼や、地元農家と連携した旬の食材の提供、太極拳やストレッチ講座の実施など、健康づくりを“日常化”する仕組みを構築。
さらに、スマートフォンアプリを活用した健康相談や睡眠チェックのフィードバックにより、従業員の健康リテラシー向上と疾病予防を同時に実現しています。
事例② 製造業×働きやすさ重視の柔軟就労モデル
社員数50名規模の製造業B社では、働きやすさと健康支援を両立する環境整備に注力。柔軟な時差出勤制度や原則定時退社のルールに加え、昼礼での健康テーマ共有や、産業医との個別面談などを通じて、メンタルヘルスにも配慮した職場文化を築いています。
健康経営戦略マップを策定し、数値目標とKPIを全社で共有することで、組織的なPDCA運用が定着しつつあります。コンパクトな組織でも健康経営の高度化は可能である好例です。
事例③ 建設業×全社巻き込み型の多面的アプローチ
建設業を営むC社では、健康経営を経営戦略の中核に位置づけ、経営層を中心とした「健康経営会議」を毎月開催。運動促進、禁煙支援、歯科検診費用の補助、ウォーキングイベントなどを通じて、従業員の多様な健康ニーズに対応しています。
社内イントラネットやアプリを活用した参加型企画により、部門を超えた交流も活発に。さらに、家計管理やライフプラン教育といった生活支援にも力を入れ、“総合的な健康支援企業”として注目されています。
まとめ:ブライト500を活用した健康経営の推進
健康経営は、中小企業にとってこそ人材確保・定着・生産性向上のカギを握る重要な戦略です。
ブライト500やネクストブライト1000の取得は、単なる称号ではなく、信頼・採用力・競争力を高める実践的な成長戦略となります。まずは健康経営への宣言からはじめ、社内の仕組みを整備することで、持続可能な企業づくりへの第一歩を踏み出すことができます。