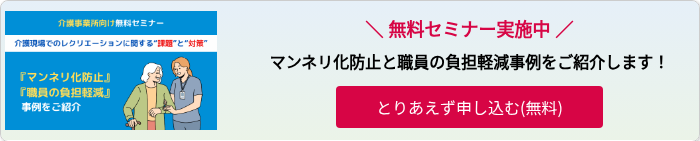デイサービスで喜ばれる!車いすでもできる「楽しい・簡単」体操プログラム

「利用者さんが飽きてしまい、レクリエーションのネタが尽きてきた…」「転倒が怖くて立位運動は避けがち。でも運動量は確保したい」そんな悩みを抱えるデイサービス・介護リハビリ施設の管理者/職員のみなさんへ。
本記事では 車いす利用者も安全に楽しめる体操メニューを、1.事前練習→2.安全確認(環境設定)→ 3.体操紹介とメニュー作成→ 4.効果測定 の4ステップ丸ごとご紹介します。明日からのレクでさっそく試せる体操メニューと、現場で役立つちょっとしたヒントとしてぜひご活用ください。
この記事を読んでいるあなたにおすすめ
事前練習
プログラムを始める前に、スタッフ自身が1回通しで動いてみましょう。
- 時間を測る – 5分以内/10分以内など目標どおりか確認
- 動きのキューイング(合図)を練習 – 「せーの」で腕上げ→下ろす、など声掛けのタイミングを合わせる
- 代替案を用意 – 片腕のみ・手拍子のみでできる“ライト版”を決めておくと、当日急な体調変化にも対応しやすい
💡ポイント
デモ時の動画をスマホで撮影し、スタッフ間で共有しておくと、シフトが違うメンバーもすぐに流れを把握できます。
安全確認(環境設定)– 安全と効果を両立する2ステップ
ステップ① 利用者の体調確認
まずは参加予定の利用者一人ひとりの体調をチェック。チェックについては、以下の3点を参考にしてみてください。
チェック項目 | 目安 |
バイタル | 血圧・脈拍・体温が基準値内 ※別表 |
姿勢保持 | 5 分程度、車いすに座ったまま姿勢を保てる |
痛みの有無 | 肩・腰・膝に急性痛がない(慢性痛は痛み止め使用状況を確認) |
項目 | 運動実施可能な目安 | 運動を控える・中止する目安 | 備考 |
収縮期血圧(最高血圧) | 90~160 mmHg | 180 mmHg以上 または 90 mmHg未満 | 安静時測定。 高血圧症の方は個別判断。 |
拡張期血圧(最低血圧) | ~100 mmHg | 110 mmHg以上 | 医師の指示があればそれに従う。 |
脈拍 (安静時) | 50~100 回/分 | 120回/分以上 または 50回/分未満 | 不整脈や頻脈がある場合は注意。 |
体温 | 36.0~37.0℃(平熱範囲) | 37.5℃以上 または平熱より+1℃以上 | 発熱や体調不良時は中止。 |
SpO₂ (酸素飽和度) | 94%以上 | 93%以下 | 呼吸器疾患の方は個別に確認。 |
自覚症状 | 安定している | めまい・息切れ・動悸・胸痛・倦怠感 などがある | 体調に不安がある場合は無理せず中止。 |
※本表は医療・介護の現場で用いられる一般的な安全基準をもとに作成しています。個別の疾患や医師の指示により基準が異なる場合があります。
出典:アンダーソン・土肥らによる運動中止基準(『内部障害理学療法学』南江堂)、厚生労働省「高齢者の健康づくり支援マニュアル」、日本心臓リハビリテーション学会ガイドライン、および臨床現場での実践的基準をもとに作成。
💡ポイント
- あいさつ代わりに「今日の体調はどうですか?」と声かけし、顔色や呼吸も観察しましょう。
- 体操の途中で体調が悪くなる場合もあります。「無理のない範囲で行いましょう」 「疲れたり、痛みを感じたら休憩したり、職員に声をかけてください」といった声かけも重要です。
- 心配な利用者は “見学参加” に切り替え、手拍子や声を出すだけでも楽しめる工夫を。
ステップ② サポート体制と環境整備
安全面をクリアしたら、次はスタッフ配置と環境整備をします。
- スタッフ1名につき、参加者 4〜6名を目安
- 転倒リスクは低いものの、手足の動きを補助できる距離感が理想。
- 車いすストッパーを必ずロック
- 足はフットサポートから下ろし床につきます。 その際、背中が背もたれにもたれないよう臀部は座面中央〜前方へ位置する。
- どうしても骨盤後傾・丸背となる場合は背中にクッションや、ミニボールを入れるなどしてサポートする。
- 足元に物を置かない
- つまずき・巻き込み防止。
- BGMの音量は“会話が聞こえる程度”
- 楽しさは保ちつつ、スタッフの声掛けがしっかり届く音量に調整。
座位でできるやさしい体操11選
車いすや椅子に座ったまま、道具なしで行える “超・手軽” なメニューを厳選しました。上半身5種と下半身6種に分けてご紹介します。
※動作はすべて呼吸を止めず、ゆっくり行うのが安全&効果アップのコツです。
※回数に関して:皆で数を数えながら行う場合は10回を目安にし、音楽に合わせて行う場合は8回ずつ行うと比較的音楽に合わせやすくなります。
上半身5種
体操名 | 主な目的と効果 | やり方 | 回数・時間 | ワンポイント |
肩回し | 肩甲骨を動かし、血流を促す 姿勢改善 | ①肘を曲げ両手をそれぞれ肩に乗せる ②肘で円を描くようにゆっくり肩を回す ※前から後へ/後ろから前へ | それぞれ4〜5回ずつ | 小さな円から少しずつ大きくする ※肩の痛みがある場合は無理のない範囲で行う |
肩甲骨寄せ | 肩甲骨を動かし、血流を促す 姿勢改善 | ①手のひらを下に向け両腕を前に伸ばす ②肘を曲げながら、肩甲骨を寄せるように後へ引く | 8〜10回 | 背中の真ん中を寄せるように引く ※肩の痛みがある場合は無理のない範囲で行う |
首のストレッチ | 首・肩こり改善 | 頭を左右に倒す 頭を左右に向ける | それぞれ10秒 | 少しずつ角度を増やす 頭の重さを使って倒す |
体側伸ばし | 肋骨周りの柔軟性を促し呼吸をしやすくする | ①肘を曲げ片手を肩に乗せる ②反対側の手は座面で支える ③肘を天井方向へ持ち上げ脇を伸ばす ④肘の上げ下げを繰り返す→少しずつ身体も側屈させる ※左右を入れ替えて同様に行う | 8〜10回 | 息を吸いながら伸ばし、吐きながら戻す |
体幹捻り | 脊柱の柔軟性の向上 内臓機能の活性化 自律神経の調整 | ①姿勢を整えて座る ②右手で左膝の外側を抑える ③左手は後の背もたれか座面を持つ ④右手で左膝を引くように体を捻る ※左右を入れ替えて同様に行う | 捻った状態で10秒キープする (捻った状態で2〜3呼吸キープ) | 背骨を真っ直ぐに整えてから行う 息を吸いながら背筋を伸ばし、吐きながら捻りを深める ※圧迫骨折中の方は捻りは行わず、背中を伸ばす |
下半身6種
体操名 | 主な目的と効果 | やり方 | 回数・時間 | ワンポイント |
かかと・つま先上げ | 足関節の柔軟性向上 転倒予防 | ①つま先(足の指)で床を押しながらかかとを上げる ②踵で床を押しながらつま先を上げる | 交互に20回 | 膝は軽く開いて安定させる どちらかを10回ずつ続けて行ってもよい |
膝伸ばし | 大腿四頭筋筋力維持・向上 | ①曲げている片方の膝を伸ばしながら足を床から持ち上げる ②伸ばす際につま先を天井に向ける ※左右を入れ替えて同様に行う | 片足8〜10回 | 膝の位置は変わらないようにして動かす(ボールやタオルを丸めて挟んで行うとやりやすい) ももに力が入っていることを確認する ※膝が痛い方は膝を伸ばしたまま行う |
膝の開閉 | 股関節可動域向上 中臀筋筋力維持・向上 | ①両足を揃える ②手で膝の外側を押さえ、両膝をゆっくり開閉 する | 8〜10回 | お尻の外側に力を入れる |
もも上げ | 腸腰筋筋力維持・向上 | ①姿勢を整える ②片足ずつももを上に持ち上げる | 20回 | 体が後ろに倒れないようお腹にも力を入れる 通常よりも高く上げる どちらかを10回ずつ続けて行ってもよい 参加者に応じて素早く上げることもできる |
ツイスト | 腸腰筋・体幹筋力向上 | ①両手を肩に乗せ横に広げる ②左足を持ち上げながら右肘と左膝をタッチ ③反対も同様に行う | 8〜10回 | 体幹の捻りを加えながら行う ※腰痛、圧迫骨折中の方は腿上げのみで行う |
足首回し | 足関節可動域向上 転倒予防 | ①片足を浮かせる ②足首からゆっくり大きく外側に回す ③同様に内側に回す | 4〜5回ずつ | 大きく丸を描くように足首から動かす |
💡安全チェック
- 姿勢が崩れたらすぐストップし、背中とお尻を椅子に密着させてリセット。
- 呼吸が止まっていないか?確認しながら進める。
- 呼吸が止まらないよう、一緒にカウントしながら行うこともできる。
- 痛みが強い動作は休憩し、手拍子・呼吸法だけでも参加OK。
体操メニュー早見表(難易度 × 所要時間)
まずは「どの利用者に、どのくらいの時間で、どんな動きをするか」をパッと選べる早見表をご覧ください。
レベル | 所要時間 | 主な対象 | 動作例 | ねらい | おすすめBGM(目安BPM) |
初級 | 約3分 | 体力に自信がない方 初参加の方 | 深呼吸 / 肩回し / 肩甲骨寄せ / 首ストレッチ | 血流促進・ウォームアップ | 80〜90 |
中級 | 約5分 | 座位で姿勢保持が安定している方 | 足踏み / もも上げ / ツイスト | 心肺機能向上・リズム感覚 | 90〜100 |
上級 | 約10分 | ゲーム感覚で楽しみたいグループ | 手拍子ゲーム / 左右同時動作 / 左右異操作 | 心肺機能向上・リズム感覚・認知刺激 | 100〜120 |
💡使い方のヒント
- 「ウォームアップ → メイン → クールダウン」の三部構成で組むと安全&効果的。
- 同じレベルでもテンポや速さを変えることでも難易度を微調整できます。
- 利用者の調子に合わせて初級+中級を組み合わせるなどのカスタマイズもOK。
初級3分コース
- 動作ステップ(例)
- 深呼吸2回
- 肩回し×前回し・後回し各5回
- 両腕を前に伸ばして引く(肩甲骨寄せ×10回
- 首を左右ゆっくり倒す×左右各5回
- ポイント:反動をつけず、呼吸を止めないよう声掛け。
中級5分コース
- 動作ステップ(例)
- その場足踏み×30秒
- 足踏みをしながら腕を上下に動かしたり、横に開いて閉じたりすることもできる
- もも上げ×左右各10回
- 足踏みと同様に腕の動きをつけることもできる
- ツイスト×左右各10回
- ポイント:スタッフがカウント+掛け声を合わせ、テンポよく進行。
- ライト版:足踏みの代わりにかかと上げでも可。腕の動きだけでも可。
上級 10分コース
- 動作ステップ(例)
- 足踏みに合わせて手拍子を行う
- 手拍子を上下や左右で行う
- 手拍子の回数を変える(上で2回・下で2回、右で2回・左で2回など)
- 足踏みで3歩目に止まる(12・・12・・→・・の箇所で止まる)
- 止まった箇所で手拍子チャチャチャを行う
- ポイント:声掛け+笑顔のリアクションでゲーム要素を強調。
- 数を数えて声を出すことだけでも十分に認知刺激◎(12チャチャチャ・・・)
- ライト版:足踏みの代わりにかかと上げでも可。手拍子だけでも可。声出しだけでも可。
※中級・上級コースの後はストレッチも行い終了しましょう。
効果測定&記録のコツ ─ “やりっぱなし”にしない仕組みづくり
なぜ測定するのか?
- 利用者の変化を可視化 → モチベーションアップ&次回メニュー選定の根拠
- 家族・ケアマネへの報告資料 → 取り組み状況を具体的に共有できる
- スタッフの振り返り → 声掛けやサポート体制を改善しやすい
※ 本格的な医学的評価(握力・歩行速度 など)は専門職と連携し、ここでは日常的に記録しやすいシンプル指標に絞ります。
おすすめ簡単 3指標
指標 | 測定タイミング | 記録方法 | 参考ポイント |
参加人数 | 毎回 | 出席表にチェック | 定員に対する参加率で盛り上がり度を把握 |
動き・疲労度 | スタッフが観察・終了直後 | 体操ができているか、疲労度は0〜10で自己申告(Borgスケール簡易版等) | できない動きが多い場合や、疲労度が5を超える場合は次回調整 |
笑顔・発話回数 | スタッフが観察 | 「笑顔/声出しがあった利用者数」をカウント | 認知刺激・楽しさの定量化に◎ |
記録シートの作り方(例)
日付 | プログラム名 | 参加人数 | 平均疲労度 | 笑顔・発話があった人数 | スタッフメモ |
6/20 | 初級 3分 | 12/15 | 3.2 | 10 | BGMで盛り上がり◎ |
6/22 | 中級 5分 | 11/15 | 4.8 | 9 | 足踏みタップで声掛け要改善 |
💡作成のポイント
- Excel/スプレッドシートで 1行 = 1セッション にすると集計しやすい
- 週または月単位で平均値を出し、グラフ化すると変化が一目でわかる
- スタッフメモ欄は「声掛けの工夫」 「利用者の反応」を具体的に残すと次回改善がスムーズ
共有とフィードバックの流れ
- セッション後 5 分以内に担当スタッフが数値を入力
- 週次ミーティングでグラフを共有し、
- 参加率が低下 → メニューを短縮 or レベル変更
- 笑顔率が上昇 → 同じBGMを次回も採用など即改善
- 月末に家族・ケアマネ向けレポートに抜粋を掲載
よくある質問 Q&A
質問 | 回答 |
Q1. 準備に必要な道具はありますか? | 基本は椅子(車いす)と音楽再生機だけで始められます。タオルを使う場合は、利用者ごとに長さ70 cm ほどのフェイスタオルを用意してください。 |
Q2. 何分ぐらい体操すれば効果がありますか? | まずは3〜5分の短時間から始めましょう。週3回程度でも「参加率」「笑顔の回数」などの定性的な変化が見えます。慣れてきたら10分コースへステップアップしても OKです。 |
Q3. 転倒やケガが心配です。安全対策は? | 「車いすストッパーをロック」「足元に物を置かない」「スタッフ 1名につき4〜6名を目安に配置」の3点を徹底すれば、リスクは最小限に抑えられます。痛みがある利用者には手拍子での参加を提案してください。 |
Q4. 体操を嫌がる利用者への声掛けは? | 「一緒に手拍子だけでもどうですか?」など “参加ハードルを下げる提案” が有効です。短いメニューを選び、好きな曲を流すと興味を示しやすくなります。 |
Q5. 認知症の方も参加できますか? | できます。単純でリズムのある動きは認知機能への刺激になり、BGMやスタッフの掛け声が「刺激 → 反応」のサイクルを促します。理解が難しい場合は、スタッフが向かい合って同じ動きを見せる「ミラー法」が効果的です。 |
Q6. スタッフが少ない日に実施するコツは? | ひとつの動きを30〜40秒ずつループする構成にすると、声掛けが単純化されスタッフ1名でも進行しやすくなります。また、スマホでデモ動画を流しながら進めると、利用者が視覚的に理解しやすくなります。 |
まとめ: “楽しい・簡単・座ったまま”の体操を明日から現場で
- 短時間 × リズム要素 のプログラムは、参加ハードルを下げて継続率を高めます。
- 利用者スクリーニング → スタッフ配置 → 声掛けの工夫 を押さえれば、安全に取り組めます。
- 参加人数・笑顔・発話回数 など “楽しさ” を定量化すれば、次の改善策も立てやすくなります。
もっと手軽に始めたい方へ
ルネサンス オンライン体操教室では、座位中心の簡単体操と脳トレプログラムをライブ配信(Zoom)しています。プロのインストラクターと一緒に、利用者さんが笑顔で体を動かせる 40分間のレッスンをご体験いただけます。
- 双方向型なので、その場で声掛けや代替動作の提案が受けられる
- スタッフ研修不要:配信中は見守りに専念でき、人手不足の日も安心
- 無料体験会を毎日 月~金曜に開催中(所要40分・Zoom利用)
詳細、お申込みはこちら