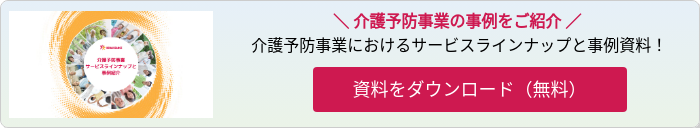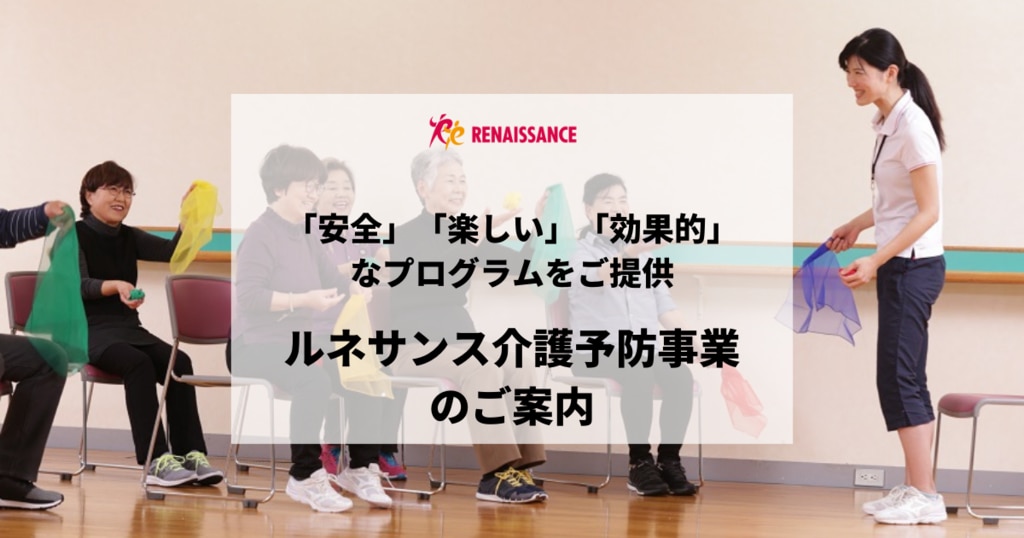介護予防を“ワクワクドキドキ”に変える新戦略|フレイル予防と住民主体モデルで地域が変わる

これからの介護予防は「従来の型にはまった支援」から、「住民が自ら参加し、楽しめる支援」へと大きく舵を切ろうとしています。フレイル予防の第一人者・飯島勝矢氏の講演内容をもとに、「介護予防×地域づくり」の新しいかたちと、その実践に役立つヒントをまとめました。本記事では、政策の変化や実践事例、地域課題の分析までを踏まえ解説します。
この記事は、東京大学 高齢社会総合研究機構 特任教授であり、フレイル予防に関する国の政策検討にも携わる飯島勝矢氏の講演をもとに構成されています。
(※本記事は、2025年5月28日に開催されたウェビナー「ウェルビーイング実現に向けた新たな介護予防戦略 〜介護予防無関心層も含めた多様な住民へのアプローチ〜」から構成された要約記事です。監修:東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長・未来ビジョン研究センター教授 飯島勝矢氏)
この記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 | フレイルの診断基準とは? フレイルの予防に活用できるプログラム
- お役立ち記事 |介護予防に有効な体操とは。自治体で取り組むプログラムの種類
国の新方針「高齢社会対策大綱 2024」が示す3つの柱
2024年に閣議決定された「高齢社会対策大綱」は、今後の日本社会における高齢者支援・介護予防の方向性を示す重要な政策文書です(参照:
https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_r06.pdf
3つの柱の要点と背景
- 年齢に関係なく活躍し続けられる社会
- 一人暮らし高齢者でも安心して暮らせる地域づくり
- 心身機能の変化に対応した切れ目ない支援体制
この柱は、孤立防止、就労支援、地域包括ケアの進化と密接に関係しており、各自治体に求められる具体的な取り組みの方向性を示しています。
フレイル予防と大綱の関係性
特にフレイル予防は、これらの大綱の柱にも深く関連しており、地域住民が自ら行動する力を育むことが政策の要とも言えるでしょう。
健康診断では見えないリスクとは
一般的な健康診断では、「血圧・血糖・コレステロール」などの生活習慣病に関する数値が中心です。しかし、フレイルに関して重要な「筋肉の質の低下(サルコペニア)」、「口腔機能の衰え(オーラルフレイル)」、「人とのつながりの希薄化(社会的フレイル)」などは、診断項目に含まれていないことがほとんどです。
講演で紹介されたエピソードでは、「健診ではすべてA判定だった男性が、実は外出頻度が週1回以下で、歩行スピードが著しく低下していた」事例が紹介されました。これは“隠れフレイル”の典型的な例ということです。数値だけを信じて「自分は大丈夫」と思い込むことが、重症化を招くリスクになります。
“隠れフレイル”に対する早期の気づきを促進
フレイルは段階的に進行するため、早期に発見・介入することで改善が十分に可能とされています。特に、本人が気づきにくい“隠れフレイル”に早期に気づくきっかけを提供することが、介護予防の観点から非常に重要です。
地域の成功事例では、毎月1回、集会所で「フレイルチェック」を中心とした「からだ測定会」が開催されています。このイベントでは、質問紙への回答、握力測定、指輪っかテスト、片足立ちテストなどを通じて、参加者が自身の身体の状態を客観的に把握できる機会を提供しています。
測定後には、結果に基づいた個別アドバイスが行われ、簡単な筋力トレーニング教室も実施されます。これにより、参加者の満足度は非常に高く、継続的な参加にもつながっています。
さらに、このイベントは「フレイルサポーター」と呼ばれる地域住民が主体となって運営しており、参加者が自分自身の健康課題として捉えやすくなる工夫がされています。
このような取り組みは、「診断して終わり」ではなく、「診断結果を次の行動につなげる」ことを重視しており、介護予防の新たなステージへの進化を示すものです。
介護予防の常識が変わる。「ワクワクドキドキ」という新発想
なぜ「ワクワクドキドキ」が求められるのか?
これまでの介護予防では、「健康のために参加しなければならない」という構図が一般的でした。体操教室や講話会など、健康情報の提供には一定の効果がありますが、参加者の関心や感情に訴える要素が乏しく、継続率の低さが課題でした。
その中で注目されているのが、“ワクワクドキドキ”という感情を軸にしたアプローチです。飯島氏は「行かなきゃいけない場所ではなく、“行きたい”と思える場づくりこそが本質」と強調します。
実際、「今日はどんな人に出会えるだろう」「こんなこともできるんだ」と思える経験が、高齢者の心に火をつけ、生活に張りを与えます。介護予防において、喜びや感動といったポジティブな感情は、モチベーション維持の源泉となるのです。
趣味を介した社会参加の促進
講演で紹介された事例の一つに、「コーヒー講座」をきっかけに始まった“珈琲サロン”があります。これは、地域住民が講師となってハンドドリップの技術を教え合う場で、参加者同士の交流が自然に生まれました。イベントの終盤には「自分の家で淹れてみた」「家族に振る舞って喜ばれた」という声が寄せられ、活動が家庭内にも波及していることがわかります。
また、ドローン講座では、操作を学ぶだけでなく「撮影した映像を持ち寄り、地域の風景展覧会を開く」活動へと発展。単なる体験ではなく、社会に“作品”として還元されるプロセスが、生きがいと誇りを生み出します。
このように、「好きなこと」や「得意なこと」を通じた参加は、身体だけでなく心理面・社会面のフレイル予防に直結するのです。
住民主体で運営するという視点
さらに重要なのが、運営の在り方です。外部講師を呼ぶのではなく、地域の住民が企画・運営の中心になることで、“自分たちの場”という意識が生まれます。
たとえば、ある地域では「手芸サークル」のリーダーを務めていた80代女性が、介護予防事業の企画委員となり、自らプログラム設計にも関わりました。「私のようなおばあちゃんでも役に立てる」と話す彼女の姿は、他の住民にとって大きな励みとなりました。
住民が主導し、共に学び、共に笑い合うプロセス自体が、“フレイル予防の実践”であると言えるでしょう。自治体の支援は、その背中をそっと押す存在であればよいのです。
まとめ:介護予防を“地域づくり”として再設計する時代へ
多職種・多主体で支える地域包括ケアの深化
医療・福祉職だけでなく、行政、企業、大学、市民団体が連携することで、多面的な支援が可能になります。地域の資源を再発見し、組み合わせることが鍵です。
フレイル予防は「自分ごと」へ
一方的な啓発ではなく、体験・共感・成功体験の共有を通じて、「自分にも関係ある」と感じさせる情報設計が今後のポイントになります。
『ルネサンス』では、フレイル予防をはじめとする地域高齢者の介護予防事業を支援するプログラムを提供しています。これまで270以上の自治体で介護予防事業を受託してきた実績を基に、通いの場の創出や健康づくりプログラムの実施、住民による自主的な活動の支援など、幅広いサポートをお任せいただけます。