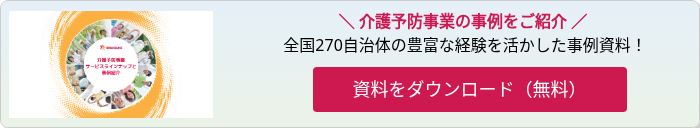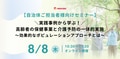フレイルの診断基準とは? フレイルの予防に活用できるプログラム

フレイルとは、加齢に伴って体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態です。日本においては、地域に在住する高齢者の約10%がフレイル高齢者とされます。また、フレイルは一般的に、健康状態と要介護状態の中間の段階に位置づけられています。
自治体の高齢福祉課の担当者のなかには、「フレイルの診断はどのような基準で行われるのか」「フレイルを予防する方法を知りたい」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、フレイルの診断基準とフレイルを予防するルネサンスのサービスについて解説します。
出典:厚生労働省『食べて元気にフレイル予防』『高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン』
こちらの記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 |フレイルとは?地域社会におけるフレイル対策について
- お役立ち記事 | 介護予防に有効な体操とは。自治体で取り組むプログラムの種類
- お役立ち記事 |介護予防を“ワクワクドキドキ”に変える新戦略
フレイルの診断基準
フレイルの診断には統一された基準はありませんが、主要な診断基準としてCardiovascular Health Study基準(以下、CHS基準)が存在し、身体的フレイルの診断に用いられます。
日本においてはCHS基準を修正した日本版CHS基準(J-CHS基準)が提唱されており、5つの項目のうち3つ以上が該当するとフレイルと診断されます。ほかにも、厚生労働省が発表している『後期高齢者の質問票の解説と留意事項』内にある15の質問票が用いられる場合もあります。
出典:厚生労働省『後期高齢者の質問票の解説と留意事項』
2020年改訂 日本版CHS基準(J-CHS基準)
項目 | 評価基準 |
体重減少 | 6か月で、2kg以上の(意図しない)体重減少 (基本チェックリスト#11) |
筋力低下 | 握力:男性<28kg、女性<18kg |
疲労感 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする (基本チェックリスト#25) |
歩行速度 | 通常歩行速度<1.0m/秒 |
身体活動 | ①軽い運動・体操をしていますか? ②定期的な運動・スポーツをしていますか? 上記2ついずれも「週に1回もしていない」と回答 |
【判定基準】
- 3項目以上に該当:フレイル
- 1~2項目に該当:プレフレイル
- 該当なし:ロバスト(健常)
(Satake S, et al. Geriatr Gerontol Int. 2020; 20(10): 992-993. )
出典:国立長寿医療研究センター『2020年改訂日本版 CHS(J-CHS基準)』
体重減少
日本版CHS基準では、6ヶ月で2〜3kg以上の体重減少がある場合にフレイルの要素として評価されます。また、BMI(※)の数値が21.5kg/m2以下の場合にも注意が必要です。
高齢期の体重減少は、肥満よりも死亡率が高くなります。65歳以上で病気でもないのに痩せてきたときには、かかりつけ医に相談したうえでメタボ予防からフレイル予防へ切り替えることが考えられます。
※肥満度を表す指数のこと。[体重kg ÷ (身長m)2]で計算する。
出典:厚生労働省『食事摂取基準(2020年版)の 策定方針について』『食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業』
筋力低下
日本版CHS基準では、握力が男性で26kg未満、女性で18kg未満の場合にフレイルの要素として評価されます。
老化に伴い筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態はサルコペニアと呼ばれ、フレイルと密接な関係にあります。サルコペニアの主な要因は加齢ですが、活動不足や疾患、栄養不良も危険因子となります。
出典:厚生労働省『食事摂取基準(2020年版)の策定方針について』『日本人の食事摂取基準(2015年版)(案)』
疲労感
日本版CHS基準では、2週間の間に訳もなく疲れたような感じがある場合にフレイルの要素として評価されます。
身体的な体力の低下だけでなく、心の病気や投薬によって疲れやすくなっているケースもあります。
出典:厚生労働省『食事摂取基準(2020年版)の策定方針について』
歩行速度
日本版CHS基準では、通常の歩行速度が秒速1.0mに満たない場合にフレイルの要素として評価されます。
歩行速度の低下は、筋力やバランス能力の低下と関連しているとされます。また、脳血管障がいや運動器疾患の影響で歩行速度が低下しているケースも考えられます。
出典:厚生労働省『食事摂取基準(2020年版)の 策定方針について』/いわき市『運動機能』
身体活動
身体活動の頻度も、フレイルを評価する際の基準の一つです。
日本版CHS基準では、身体活動を評価するために以下の2つの質問を行います。
▼日本版CHS基準における身体活動に関する質問
- 軽い運動・体操をしていますか?
- 定期的な運動・スポーツをしていますか?
2つの質問のどちらに対しても「週に一回もしていない」と回答した場合に、フレイルの要素として評価されます。
出典:厚生労働省『食事摂取基準(2020年版)の策定方針について』
フレイルを予防するには
フレイル予防のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
スポーツやボランティアなどを積極的に行っていると、健康維持や認知症リスクの減少が期待できるという報告もあります。これらの活動により心身的に充実してフレイル予防になるほか、生活機能や運動機能の向上も期待できます。
バランスの取れた栄養のある食事
健康を維持するには、バランスの取れた食事が大切です。特にたんぱく質やカルシウム、ビタミンDなどを積極的に摂取することで、筋肉や骨の衰えを防ぐのに役立つとされています。
また、口腔ケアにより口腔機能を向上させることも、心身の機能維持に繋がります。
身体活動
ウォーキングやストレッチなど、適度な運動習慣をつけることがポイントです。
無理のない範囲で日常的に取り入れましょう。
社会参加
サークル活動やボランティアへの参加によって、外出や運動の機会が増え、心の健康維持にも役立ちします。趣味や就労など、社会的なつながりがポイントとなります。
なお、地域社会におけるフレイル対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
まとめ
この記事ではフレイルについて以下の内容を解説しました。
- フレイルの診断基準
- フレイルを予防するためのポイント
フレイルの主要な診断基準として、CHS基準が存在します。日本においては日本版CHS基準が提唱されており、体重減少、筋力低下、疲労感、歩行速度、身体活動の5項目のうち、3つが該当した場合にフレイルと診断されます。
フレイルの予防にあたっては、栄養・身体活動・社会参加の3つが重要なポイントです。バランスのとれた食事や運動、ボランティアによる社会との関わりなどを通して、フレイルの予防が行えます。
また、フレイルは、自分の健康状態の把握、適切な介入によって、その状態を改善できる可能性を持つ可逆的な状態です。栄養バランスの改善や運動習慣の定着など個々の状態に合わせた取り組みを継続することで、健康状態に戻すことができます
『ルネサンス』では、フレイル予防をはじめとする地域高齢者の介護予防事業を支援するプログラムを提供しています。これまで270以上の自治体で介護予防事業を受託してきた実績を基に、通いの場の創出や健康づくりプログラムの実施、住民による自主的な活動の支援など、幅広いサポートをお任せいただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。