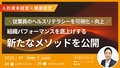職場を守るラインケアとは?人的資本時代の健康戦略

この記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 | メンタルヘルス不調につながるストレスのサインとは? 適切な対策法も解説
- お役立ち記事 | 人的資本投資とは?健康経営との関係と重要性
- お役立ち記事 | 職場における健康づくりの重要性。事例から学ぶ健康経営の取り組み
目次[非表示]
- 1.定義と目的
- 1.1.厚労省が定義する「ラインによるケア」
- 1.2.「4つのケア」とは
- 2.なぜ今、ラインケアが注目されているのか?
- 3.ラインケアはメンタルヘルス対策の一環として基本である
- 4.ラインケアの具体的な進め方
- 5.ヘルスマネジメントの知識は、今後より求められる力へ
- 6.よくある課題とその乗り越え方【事例で解説】
- 6.1.対応が属人的でうまくいかなかったケース
- 6.2.eラーニングで効果が出た企業の事例
- 6.3.ラインケアを職場に根付かせるために
- 6.4.社外の力を借りる選択肢
- 7.ラインケアが企業にもたらすメリット
- 7.1.離職率の低下と職場定着率の向上
- 7.2.訴訟リスク・企業イメージ毀損の回避
- 7.3.人事部門のリスクマネジメント強化
- 7.4.人的資本の健全な維持と価値の最大化
- 7.5.エンゲージメント向上による組織生産性の強化
- 8.まとめ
定義と目的
厚労省が定義する「ラインによるケア」
厚生労働省は、企業におけるメンタルヘルス対策を効果的に進めるために、「4つのケア」を軸とした包括的アプローチを提唱しています。このうちラインケア(ラインによるケア)は、管理監督者が部下の心の健康状態に目を配り、日常的にメンタルヘルスに配慮する行動として明確に位置づけられており、メンタルヘルス対策の最前線を担う重要な要素です。
参照:ラインによるケアとしての取り組み内容(厚生労働省)
「4つのケア」とは
- セルフケア労働者自身がストレスへの気づきや対処、ストレスコーピング行動を学び、自らの心の健康を維持・増進すること。
- ラインによるケア(ラインケア)上司や管理職が日常のコミュニケーションやマネジメントを通じて、部下のストレスサインを早期に察知し、必要な支援や環境調整を行うこと。現場の一次対応として最も基本的で実践的なケアとされます。
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア産業医、保健師、看護師、衛生管理者など、社内の専門職による相談対応や予防的介入、環境改善への助言。
- 事業場外資源によるケアEAP(従業員支援プログラム)や外部カウンセラー、医療機関など、外部の専門機関と連携した支援の活用。
なぜ今、ラインケアが注目されているのか?
ラインケアは以前から厚生労働省が推進するメンタルヘルス対策の一つとして位置づけられてきましたが、近年、職場におけるメンタルヘルスの悪化や多様化する従業員課題に対応する上で、改めてその重要性が再認識されています。
その背景には、以下のような複数の要因があります。
メンタルヘルス不調による労働災害・離職の増加
厚生労働省のデータによれば、うつ病や適応障害による精神障害の労災請求件数は年々増加傾向にあります。また、厚労省の「令和4年労働安全衛生調査」によると、メンタル不調による休職や退職を経験した事業場の割合は過去10年で着実に増えています。
このような傾向は、職場内での早期発見・早期対応の必要性が高まっていることを示しており、一次予防としてのラインケアの機能が強く求められる要因となっています。
職場内でのストレス要因の複雑化
従来は「長時間労働」や「上司のパワハラ」などが主要なストレス要因とされていましたが、近年はテレワークの導入、役割の曖昧化、組織のフラット化などにより、心理的ストレスの性質が多様化しています。
- 「誰にも相談できない孤立感」
- 「成果主義やジョブ型雇用による競争プレッシャー」
- 「職場の人間関係が希薄で、異変に気づかれにくい」
このような状況では、表面的な不調ではなく“見えづらい不調”を管理職が早期に察知する力が一層重要になっており、ラインケアの実効性が問われています。
ハラスメント対策義務化と安全配慮義務の強化
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)により、企業には職場のハラスメント防止体制の構築が義務化されました。これに伴い、管理職が現場の異変に気づかず対応を怠ったことが、企業の法的責任や損害賠償リスクに直結するという認識が広まりつつあります。ラインケアは、こうした「リスクの予兆」に気づき、早期に手を打つ体制の中核を担うものとして注目を集めています。
エンゲージメント向上と人的資本経営の時代へ
人的資本経営(Human Capital Management)が国際的な潮流となり、企業も「従業員の健康と働きがい」を経営戦略の中核に据えるようになってきました。厚生労働省や経済産業省も「健康経営」「働き方改革」「女性活躍」などの政策を通じて、従業員のウェルビーイングの実現を支援しています。
こうした時代において、従業員一人ひとりの声を拾い、信頼関係を築く管理職の存在が不可欠であり、ラインケアは“現場での人的資本マネジメントの入口”として再注目されているのです。
人的資本投資と健康経営の関係と重要性については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
ラインケアはメンタルヘルス対策の一環として基本である
ラインケアは、企業におけるメンタルヘルス対策の柱であり、一次予防(未然防止)の観点から非常に重要な役割を担うものです。従業員の小さな変化に気づき、早期に支援につなげることが、不調の深刻化や長期休職の防止につながります。
そのため、ラインケアは法令上の義務ではないものの、厚生労働省が「心の健康づくり計画指針」において事業者に努力義務として強く推奨している取り組みです。特に、管理職がラインケアの担い手となるためには、基礎的なメンタルヘルスの知識と対応スキルを身につけることが前提となります。ラインケアは、企業におけるメンタルヘルス対策の柱であり、一次予防(未然防止)の観点から非常に重要な役割を担うものです。従業員の小さな変化に気づき、早期に支援につなげることが、不調の深刻化や長期休職の防止につながります。
また、メンタルヘルス不調に繋がるストレスのサインと、その適切な対策法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
ラインケアの具体的な進め方
日常のコミュニケーションの中でできる気づき
ラインケアは特別な場面で行うものではなく、普段の何気ないやり取りの中での気づきが出発点です。遅刻や表情の曇り、口数の減少、報告の簡素化など、些細な変化がメンタル不調の初期サインであることも少なくありません。雑談や朝礼、業務報告など、日常の接点を丁寧に観察する意識が、早期発見につながります。違和感を覚えたら、「気のせい」ではなく、小さな兆候として捉えることが重要です。
声かけ・面談時のポイント
気になるサインに気づいた際の声かけは、信頼関係を築くか、警戒させてしまうかの分かれ道になります。「最近様子が違うように感じるけど、大丈夫?」といった観察をベースにした具体的な声かけや、「疲れているように見えるけど無理してない?」など、相手に寄り添う言葉選びが大切です。面談の際は評価とは切り離し、「話してよかった」と思えるよう、安心感と非評価の姿勢を意識しましょう。
必要に応じた人事・産業保健スタッフとの連携
気になる様子が続く、あるいは不調が疑われる場合は、管理職一人で抱え込まず、早めに人事や産業保健スタッフ(産業医・保健師)と連携することが重要です。この際、従業員のプライバシーに十分配慮しながら、業務への影響やサポートの必要性など、事実ベースでの情報共有が求められます。相談のハードルを下げる意味でも、日頃から産業保健職や人事との信頼関係を築いておくことが、迅速な対応につながります。
ヘルスマネジメントの知識は、今後より求められる力へ
- 定期健康診断の結果を踏まえた適切なフォロー(事後措置)
- 私傷病(仕事以外が原因の病気やケガ)への配慮と対応
- 女性従業員の健康問題(PMS、妊娠・出産、更年期など)への理解
- 高年齢従業員に対する健康確保と職場環境整備
- 労働安全衛生法でまだ十分に規定されていない課題への対応
よくある課題とその乗り越え方【事例で解説】
対応が属人的でうまくいかなかったケース
ラインケアの導入が進んでも、現場での実践が「管理職の個人差」によって左右されるケースは少なくありません。たとえば、ある企業では、部下の不調にいち早く気づいて面談や支援につなげた管理職がいた一方で、別の部署では同様のサインを見逃し、結果としてメンタル不調の悪化や長期休職を招いてしまったという事例がありました。こうしたばらつきは、組織内に「支援の不平等感」や「放置されるかもしれないという不信感」を生む温床となります。このような課題を克服するためには、ラインケアを「人任せ」や「経験に頼る」ものから脱却させる必要があります。具体的には、
- 社内で統一的な対応指針(ガイドライン)の整備
- 「このような場合はこう対応する」というシナリオ形式の研修の導入
- 管理職間での事例共有会や相互フィードバックの実施
といった方法で、組織全体としての対応力を平準化し、属人的なリスクを減らすことが重要です。
eラーニングで効果が出た企業の事例
ある中堅製造業の企業では、ラインケア研修が年1回の集合型研修のみだったため、「受けただけで終わる」「現場ではどうすればいいか分からない」との声が相次いでいました。
特に多忙な管理職ほど、実務に活かせず「自信が持てない」と感じていたのです。そこで、eラーニング形式の教育プログラムを導入し、1本10分程度の短時間動画で基本知識を反復学習できる仕組みを構築しました。さらに、研修修了後にはオンラインテストを実施し、理解度を可視化。その後、人事と1on1の面談で「どのような場面で使えそうか」を話し合う時間を設けることで、実践に結びつけました。結果として、管理職からは「対応への不安が減った」「判断の軸が持てるようになった」というポジティブな反応が得られました。
このように、eラーニングは
- 標準化されたコンテンツの反復学習が可能
- 自分のペースで学べるため多忙な層にも有効
- 集合研修では得にくい継続性や実践性を確保できる
といったメリットから、ラインケア教育の基盤として非常に有効です。
ラインケアを職場に根付かせるために
ラインケアは、1回の研修やマニュアルの配布だけで定着するものではありません。むしろ、実務の中で試行錯誤を繰り返しながら、自分なりの関わり方を築いていく支援行動です。そのためには、継続的かつ段階的な教育設計が必要不可欠です。
具体的な施策としては、
- 新任管理職向けの導入研修(着任時に実施)
- ロールプレイやケース検討を取り入れた応用研修
- 半年〜1年ごとのフォローアップ研修や相談会
- ラインケア実施状況を可視化し、上司が部下から信頼されているかをフィードバック
などを通じて、「知っている」から「できている」へと段階的に支援スキルを高めていく必要があります。こうした取り組みにより、ラインケアは単なる知識ではなく、職場文化の一部として定着していくことが可能になります。
社外の力を借りる選択肢
社内のリソースや体制だけでは、すべてのラインケア課題に対応しきれない場面も少なくありません。管理職や人事担当者の経験・知識には限界があり、制度を継続的に機能させるには社外の専門機関やプロフェッショナルとの連携が重要です。とくに次のような場面では、外部の支援を活用することで、対応の質・精度・継続性が大幅に向上します。
- 産業医・外部カウンセラー・臨床心理士による専門的対応複雑なメンタル不調ケースや職場復帰支援において、専門職による判断や助言は、社内では得られない中立性と信頼性を提供します。
- EAP(従業員支援プログラム)の活用第三者相談窓口として、従業員が上司や人事には話しにくい内容を安心して相談できる場を提供します。早期相談・早期介入の仕組みが整うことで、メンタル不調の重症化や突発的な離職を未然に防ぐ効果があります。
- 復職支援や職場復帰調整など、複数部署にまたがる高度対応本人、上司、産業医、人事との間に立って調整できる外部ファシリテーターの存在が、社内調整負荷の軽減に寄与します。
- 外部研修講師による、管理職向けのラインケア教育の強化特に初めてラインケアを学ぶ管理職にとって、社外の専門講師による研修は、専門的かつ実践的な知見を得られる絶好の機会です。社内では語りにくい失敗事例や最新の動向、法律リスクへの理解を促すことができ、受講者の納得感と危機感の醸成に効果があります。加えて、社外講師の導入には「組織としてラインケアを重視している」というメッセージ性が伴い、研修そのものが組織文化変革の契機となる点でも意義があります。定期開催や階層別研修と組み合わせることで、ラインケアの教育を制度化・文化化する土台づくりが可能です。
このように、外部支援を追加コスト”ではなく、“制度の信頼性と実効性を保証する戦略的投資”と捉えることが重要です。人的資本経営が求められる時代においては、社内外の支援体制を構築・開示すること自体が、企業価値の証明にもなります。
ラインケアが企業にもたらすメリット
離職率の低下と職場定着率の向上
メンタルヘルス不調を早期に察知し、適切な支援を行うことで、休職や退職といった重大な結果を未然に防ぐことが可能になります。職場で「自分の変化に気づいてくれる人がいる」という安心感が醸成されると、従業員の信頼や心理的安全性が高まり、結果的に定着率が向上します。これは中途採用・再教育などのコスト削減にもつながり、組織の人材維持コストに対する投資対効果も高い施策です。
訴訟リスク・企業イメージ毀損の回避
ラインケアを怠った結果、メンタル不調者への不適切対応やハラスメントの見逃しが発展して訴訟に至るケースもあります。法的には「安全配慮義務違反」が問われ、企業名の公表やブランド毀損、採用難など長期的ダメージを招く可能性も。ラインケアの徹底は、企業防衛策としてだけでなく、社会的信頼の維持・向上にも不可欠な要素です。
人事部門のリスクマネジメント強化
現場の管理職がラインケアを実践することで、人事部門は“事後対応”から“予防的支援”へと役割をシフトできます。産業医や保健師、人事担当者が管理職と連携して問題を共有する体制が整うことで、組織全体としてのリスク感度と初期対応力が向上。これにより、個別の労務トラブルを早期にコントロールできる柔軟な組織運営が実現します。
人的資本の健全な維持と価値の最大化
近年、ISO30414や人的資本可視化指針により、従業員の健康・エンゲージメント・離職率などが“投資家が評価する経営情報”として公開対象となっています。ラインケアは、これらの指標を現場から支える「人的資本の健全性を維持する仕組みづくり」といえます。従業員の心身の健康と働きがいが守られることで、人的資本が単なる“リスク”ではなく“価値を生み出す源泉”として活用される基盤が整います。
エンゲージメント向上による組織生産性の強化
ラインケアは、単なる不調者への対応ではなく、すべての従業員に対して「見守られている」という安心感とつながり感を提供します。上司との関係性が良好な環境では、部下の主体性や挑戦意欲が高まりやすく、組織のエンゲージメント指標が向上する傾向にあります。これは、生産性やイノベーション創出、職場の協働性といった無形資産の価値向上にもつながる重要な基盤となります。
まとめ
ラインケアとは、管理職が現場で実践するメンタルヘルスケアの中核であり、従業員の心身の変化を見逃さず、早期支援へとつなげる仕組みです。現代の多様化する働き方や価値観において、単なる“メンタル不調の対応”ではなく、「信頼と対話を通じた人的資本の活性化」として位置づけられています。組織としてラインケアを制度化・文化とすることは、従業員の安心と企業の信頼性を同時に高める戦略的投資であり、経営における新たな責務といえるでしょう。
職場のメンタルヘルス対策の促進に向けて、従業員へのセルフケアの指導をはじめ、健康づくりの支援、不安や悩みを相談できる体制を整備してはいかがでしょうか。
ルネサンスが提供する健康経営支援サービス『スマートAction』では、NPO法人健康経営研究会 理事長・産業医である岡田邦夫氏が登壇する「管理職のためのヘルスマネジメントセミナー」を受講いただけます。このセミナーは、健康経営度調査における「管理職向けセミナー」全項目にチェックが入る設計となっており、実効性と網羅性の両面で高い評価を得ています。その他メンタルヘルスケアをはじめ、健康リテラシー向上のためのeラーニングやセミナーの実施、健康アドバイス・アプリの提供など、ご要望に応じたソリューションで健康課題の解消に貢献いたします。
「管理職の対応力を底上げしたい」 「健康経営の取り組みを仕組み化・可視化したい」といった課題をお持ちの企業様は、お気軽にご相談ください。