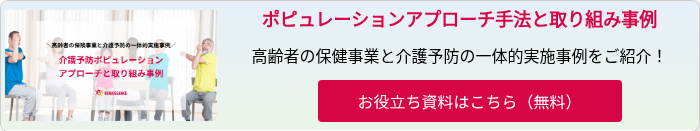高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施におけるポピュレーションアプローチとは?|自治体職員が知っておきたい基礎と実践

その他、この記事を読んでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事:厚生労働省が推進する保健事業と介護予防の一体的実施とは?
- お役立ち記事:厚生労働省が提唱する通いの場とは?効果と運営方法を紹介
なぜ今「一体的実施」と「ポピュレーションアプローチ」が注目されているのか
要介護・要支援者の増加と地域生活の選択肢制限
少子高齢化が加速する中、要支援・要介護状態の高齢者が増加し、「できるだけ住み慣れた地域で暮らし続けたい」というニーズが強まっています。しかし、支援が必要になると、通院や買い物といった日常行動に制限が生じ、「選択肢」が大きく減るという課題が浮き彫りになっています。
多様な主体による協働・制度的背景の整理
こうした背景から注目されているのが、ポピュレーションアプローチを軸にした地域全体への働きかけです。これは、特定のリスクを抱える層だけを対象にするのではなく、住民全体を対象にした介入であり、「重度化予防」と「孤立防止」にもつながる包括的な考え方です。
また、2025年以降、団塊の世代が75歳を迎える中で、専門職だけで支えきる構造には限界があるといった問題意識も高まりつつあります。医療・介護の専門性を活かしながら、地域住民やNPO、企業など多様な主体が連携する「一体的実施」の必要性が、制度的にも後押しされています。
「ポピュレーションアプローチ」と「一体的実施」は、今や選択肢ではなく、地域づくりの基盤として再定義されつつあるのです。
ポピュレーションアプローチの基本概念と自治体施策への活用
アプローチの定義と得られる効果
ポピュレーションアプローチとは、特定の疾患やリスクを持つ個人に限定せず、地域住民全体を対象として健康づくりや予防介入を行う方法です。対象を絞らないことで、より多くの人々にとって支援の「入り口」を広げることができ、健康格差の縮小や早期介入による重度化防止にもつながります。
このアプローチは、地域住民の潜在的な健康課題にもアプローチできるため、医療・介護の負担軽減や、地域資源の有効活用といった点でも高く評価されています。具体的には、「通いの場」や「地域サロン」など、日常生活に組み込まれた場づくりがその代表例です。
ハイリスクアプローチとの違いと使い分け
一方で、ハイリスクアプローチは、リスクが明確に高い個人(要支援者、要介護者、既往歴を有する者など)を対象に、専門職が集中的な支援を行うものです。個別性の高い支援が可能であり、症状の進行や生活機能の低下が深刻化する前に対処できるという利点があります。
ただし、ハイリスクアプローチは対象者が限られる分、地域全体への波及効果には限界があります。そのため現在では、「ポピュレーションアプローチを基盤としながら、必要に応じてハイリスク層には個別対応を加える」という両アプローチの併用・段階的活用が、自治体実務における現実的な戦略とされています。
一体的実施の推進においても、このような視点を持つことで、より柔軟かつ包括的な支援設計が可能になります。
ポピュレーションアプローチの実践と事例で見る地域施策の展開
ポピュレーションアプローチは、特定のリスク層だけでなく、地域住民全体に働きかける包括的な手法です。一体的実施の現場では、この考え方をもとに様々な形で制度運用が進められています。ここでは、実際の導入形態と、それに基づいた自治体の事例をあわせて紹介します。
地域での導入形態(通いの場・予防拠点)
一体的実施におけるポピュレーションアプローチの中心的な施策の一つが、「通いの場」の活用です。これは地域の公民館やサロンなどで、住民が自由に参加できる場を設け、運動・栄養・口腔ケア・交流といった健康支援を提供するものです。
特徴的なのは、単なる健康講座ではなく、専門職が現場に出向き、フレイル兆候の早期発見や生活習慣の改善を促す働きかけを継続的に行っている点です。
- 椅子体操や軽運動など、初心者でも参加しやすい設計
- 健康ポイント制度を活用した参加継続へのインセンティブ
- 離脱者への個別フォローアップ体制の整備
また、こちらの記事では通いの場について詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
実践事例(墨田区/厚労省/福島県)
①墨田区|通いの場等への栄養・口腔ケア講師派遣事業
東京都墨田区では、栄養士や歯科衛生士が地域の通いの場に派遣され、参加者に対して口腔ケアや栄養に関する講話を実施しています。これは、フレイルの兆候を早期に把握し、本人の気づきを促すことを目的としています。
- 専門職による訪問形式の支援
- 地域住民の参加動機を生むプログラム設計
②厚生労働省マニュアル掲載事例
前述の厚生労働省マニュアルでは、全国各地の自治体が導入している「通いの場」の成功例がまとめられています。健康ポイント制度や、買い物支援と連動した運動教室の事例など、地域に応じた多様なアプローチが評価されています。
出典元: 「通いの場の課題解決に向けたマニュアル」
③福島県|市町村先駆的健康づくり実施支援事業
福島県では、県主導で市町村の取り組みを支援し、地域の特性に応じた健康づくり事業を多数展開しています。住民の自己選択と継続的参加を促すために、参加前後のアンケートや生活チェックを取り入れた工夫も導入されています。
このように、ポピュレーションアプローチは一体的実施の中核施策として各地で実装されており、「住民を巻き込む設計」と「継続的な関与」が成功の鍵であることが見えてきます。
ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの共存モデルへ
これまで一体的実施の基盤として紹介してきたポピュレーションアプローチは、住民全体を対象にした“広く浅い”介入を得意とする手法です。これに対し、ハイリスクアプローチは、既に要支援・要介護認定を受けた方、またはその可能性が高い個人に対して、“集中的かつ専門的”に支援を行うものです。
本来この2つのアプローチは対立するものではなく、目的と対象によって使い分ける「補完関係」にあります。
予防から継続支援へとつなげる支援設計
地域の通いの場や健康教室などで住民の健康状態や生活習慣を把握し、一定のフレイル傾向や生活課題が見られる場合には、保健師や介護予防支援専門員などの専門職による「個別的支援」への接続が行われます。
このように、「ポピュレーションアプローチによる緩やかな観察」と「ハイリスクアプローチによる的確な支援」を段階的に連動させるモデルが、今後の地域包括ケアの主流になると想定されます。
制度設計における複眼的アプローチの重要性
厚生労働省が推進する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」も、この2つのアプローチを明確に使い分ける制度ではなく、健診データや質問票を用いて“ゆるやかに層別化”し、個別支援に自然につなげる構造を採用しています。
この考え方は、以下のような制度構造に現れています。
- 特定健診 → フレイルチェック → 通いの場や教室への案内(ポピュレーション)
- 経過観察や課題あり → 保健師・ケアマネの面談支援(ハイリスク)
このように、自治体が「どちらか一方」ではなく、アプローチを段階的・複眼的に設計することが、今後の制度運用において重要な鍵となるのです。
自治体職員が今後備えるべき視点と具体行動
ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの共存を前提とした一体的実施が進むなかで、自治体職員には従来以上に“計画と現場をつなぐ”多面的な視点が求められています。制度理解だけでなく、実装・評価・説明という運用力の強化が重要です。
多層的なアプローチ設計とその実行
一体的実施の成功には、対象者を絞らず“広く構えて、必要な人に深く届ける”設計が不可欠です。そのために自治体職員は以下のような視点を持つ必要があります。
- 「通いの場」「健診」「教室」など各種活動を点で設計せず、線でつなぐ発想
- 健康無関心層にも届くような誘因設計(インセンティブ・きっかけ)
- ハイリスク層へのスムーズな段階的支援導線(モニタリング)
こうした施策設計は、保健事業と介護予防の橋渡し役として、自治体職員が主導する必要があります。
議会・関係部署・住民への説明に使える論点整理
制度の導入や施策変更にあたっては、上司や議会、他部署への説明が必須となります。その際には、制度背景だけでなく「地域の声」や「成功事例に基づく説得力のある仮説」が不可欠です。
- 参加者の満足度/行動変容データ(例:アンケート結果)
- 他自治体の成功要因(専門職活用/住民主体性の確保)
- 財政インパクト(重度化予防による介護費抑制見込み)
こうしたデータや事例を「説明資料」や「議会答弁用メモ」に落とし込む支援ツールとしても、本記事で紹介している公的事例リンクやホワイトペーパー(事例集)の活用が有効です。
まとめ|地域全体を巻き込む一体的実施で、今求められる包括ケアを実現
少子高齢化が進むなかで、地域の中で高齢者を支える仕組みには、「広く支援の網を張るポピュレーションアプローチ」と「必要な場面で個別に支えるハイリスクアプローチ」の両立が求められています。
こうした視点をつなぐ制度として、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施が全国で本格化し始めています。特定健診、通いの場、フレイル予防、専門職の関与…。これらをバラバラに進めるのではなく、地域の中で有機的に連携させる視点がこれまで以上に重要になってきています。
とはいえ、自治体ごとに置かれている環境や課題はさまざまです。
- どのような施策から始めればよいのか分からない
- 通いの場に参加してもらう仕組みづくりが難しい
- 専門職の支援を呼び込みたいが体制が整わない
そんなお悩みに対し、ルネサンスでは各自治体の課題に応じたワンストップ支援を行っています。企画立案から部署間連携、専門職派遣、そして効果検証まで、一貫した支援体制でサポートいたします。
実際に一体的実施に取り組む自治体の具体例をまとめた「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」事例集を無料で公開中です。
- 人口規模別の事例紹介(運動・講話の実践内容)
- アンケート・質問票を通じた効果検証の取り組み
- 行動変容を促すヒントと支援体制の工夫
など、すぐに現場で使える内容を豊富に掲載しております。ぜひご活用ください。