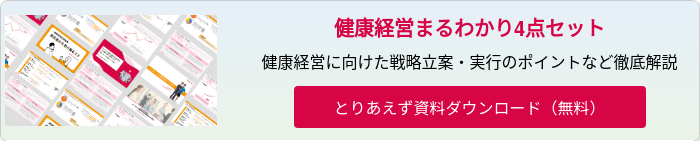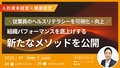健康経営と両立支援~2025年改正・育児介護休業法と企業の対応ポイント~

この記事をよんでいるあなたにおすすめ
- お役立ち記事 | 企業が両立支援を行う意義とは。具体的な取り組みや助成金制度について
- お役立ち記事 | プレコンセプションケアとは。企業による啓発活動の必要性と取り組み
はじめに|2025年問題が突きつける社会と企業の課題
2025年、日本社会はすべての団塊世代が75歳以上となり、医療・介護・看護のニーズが爆発的に増加する「2025年問題」に直面します。これにより、働きながら家族の介護を担う「ワーキングケアラー」や、育児と介護を同時に担う「ダブルケア層」の増加が顕在化し、企業にとっても深刻な人的資本の損失リスクを抱える時代が到来しています。
こうした背景のもと、2025年4月施行の「育児・介護休業法」改正は、従業員のライフステージに寄り添うだけでなく、企業にとって「健康経営」や「人的資本経営」「共生社会の実現」につながる戦略的対応が求められる重要な転機です。
本稿では、法改正のポイントと企業が講じるべき対応策、厚生労働省が示す「介護支援プラン」の導入方法を踏まえ、両立支援が従業員の働きがいと企業の持続可能性にどう貢献するのかを解説します。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法は、育児や介護と仕事を両立できる環境を整えることを目的とし、1995年に施行されました。以降、少子高齢化の進展や多様化する働き方を踏まえ、たびたび改正が行われてきました。その根底には、「ライフイベントを経験しても働き続けられる社会」の実現という理念があります。
2025年4月施行の改正ポイント
2025年4月からの改正では、企業に対して両立支援体制の強化と柔軟な働き方の整備が求められます。育児・介護に関する主な改正内容は以下のとおりです。
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
◇ 育児関連
- 柔軟な働き方の措置義務化(3歳~就学前):短時間勤務やフレックスタイム、テレワークなどを講じることが企業に義務づけられます。
- 子の看護休暇の拡充:対象が「小学校3年生修了」まで拡大され、予防接種や健康診断の付き添い、学級閉鎖時の対応も対象となります。
- 残業免除の対象拡大:小学校就学前までの子どもを育てる労働者が新たに対象となります。
- 育児目的のテレワーク導入(努力義務):特に3歳未満の子を持つ従業員について、テレワークを活用できる環境整備が求められます。
- 育児休業取得率の公表義務拡大:301人以上の企業において、男性の育児休業取得率の公表が義務化されます。
◇ 介護関連
- 介護休暇の取得対象拡大:雇用期間6か月未満の従業員も対象となります。
- 介護休暇の柔軟化:時間単位・半日単位など、利用しやすい形で取得できるよう制度が見直されます。
- テレワークの導入努力義務(介護目的):介護を担う従業員に対し、テレワーク導入が努力義務として追加されます。
- 雇用環境整備の義務化:企業は以下のいずれかの措置を講じることが求められます。
- 制度の周知
- 相談窓口の明示
- 両立支援に関する研修の実施
- 制度利用を促進する方針の策定と社内公表
この法改正を通じて、国は「誰もが家庭と仕事を無理なく両立できる社会」の実現を目指しています。企業は制度整備だけでなく、実際に利用しやすい運用体制を構築することが不可欠であり、健康経営・人的資本経営の観点からも重要な対応です。
企業に求められる対応チェックリスト
- 就業規則・制度文書の改訂と全社周知:改正内容を反映させた就業規則や関連規程を見直し、全社員に対して丁寧な説明と周知を行うことで、制度の理解と利用促進につなげます。
- 柔軟な勤務制度(時短・フレックス・テレワーク等)の整備:育児・介護の両立を可能にする柔軟な働き方を制度化し、多様なニーズに対応できる勤務環境を整備します。
- 管理職研修による対応力向上:ラインケアの観点も含め、現場の上司が部下の相談に適切に応じ、制度利用をサポートできるようにすることが重要です。
- 制度利用促進のための情報発信・人事面談:イントラネットや説明会などを活用し、従業員が制度を「知って」「使える」状態をつくるためのコミュニケーションを強化します。
- 実態把握とサーベイによるニーズの可視化:定期的な社内アンケートや個別ヒアリングを通じて、従業員が直面する育児・介護課題を把握し、制度設計や支援方針に反映させます。
厚生省「介護支援プラン策定マニュアル」に基づく実務対応
企業が従業員の介護と仕事の両立を支援するためには、厚生労働省が提示する「介護支援プラン策定マニュアル」を参考に、計画的かつ段階的な対応が求められます。ここでは、支援のフェーズごとに企業が取り組むべき実務対応を解説します。
フェーズ1:事前準備
- アンケート等での介護リスクの把握:従業員の家族構成や年齢、居住地などの情報から将来的に介護が必要になる可能性を早期に見極めることで、事前の支援準備が可能になります。
- 「支援ガイド」や「面談シート」の整備と社内掲示:従業員が安心して制度を利用できるよう、ガイドブックや記入様式をあらかじめ準備し、イントラネットなどで可視化しておくことが効果的です。
- 管理職・従業員への研修実施と職場文化の醸成:介護への理解を深めるための研修を実施し、「お互い様」の文化を醸成することが、相談のしやすさや制度の活用につながります。
フェーズ2:申し出時
- 個別面談での状況把握と柔軟な支援策の設計:介護の状況や家族の事情を丁寧にヒアリングしたうえで、勤務時間の調整や業務配分の見直しなど、個別最適な対応を検討します。
- 「面談記録兼支援プラン」の作成・共有:面談内容を文書にまとめ、従業員と人事・上司で共有することで、支援の透明性と継続性を確保します。
- 制度の即時適用と円滑運用:必要な支援策はすぐに適用し、制度を使いやすくすることで従業員の不安を軽減し、業務の継続を支えます。
フェーズ3:支援の継続
- 定期的なフォローとプラン見直し:介護状況は時間とともに変化するため、定期的な面談やプランの再確認が欠かせません。
- メンタルケアと外部支援機関(EAP等)との連携:心身の負担を軽減するために、社内の相談体制だけでなく、外部の専門機関との連携も重要です。
- 成功事例の社内共有と支援文化の定着:制度を活用した好事例を共有し、実際に使える制度として従業員の信頼を高め、社内文化として根付かせることが大切です。
健康経営視点で見る法改正の意義
本改正は、単なる法令順守にとどまらず、働きがいや健康、定着率、生産性の向上といった経営成果に直結する戦略的取り組みです。特に以下の層への対応が鍵となります。
ワーキングケアラーとは
家族の介護を担いながら働く人々で、団塊ジュニア世代に多く、介護保険の対象外となる「見えにくいケア」や「サイレントな負担」を日常的に担っています。 これらには、以下のような介護支援が含まれます。
- 通院や検査の付き添い:医療機関への送迎や待機など、時間的拘束が長くなりがちです。
- 金銭管理や行政手続き:年金・保険・介護申請など複雑な事務作業を家族が代行します。
- 家事や衛生管理:食事の用意、洗濯、清掃、排泄支援など生活のあらゆる部分を支える作業です。
- 安否確認・見守り:日常的な電話連絡や訪問、緊急時対応など、精神的な緊張を伴う見守り行動も含まれます。
- 曖昧な判断・感情労働:「何が必要か」を常に考え、本人の気持ちを汲み取る気遣いや感情労働も負担の一部です。
これらは、全てが介護保険の給付対象には含まれないため、制度上の支援が届きにくい“サイレントなケア”として企業の理解と支援が不可欠です。
ダブルケアの深刻化
30~50代前半の中核人材が、幼い子どもの育児と親の介護を同時に担うダブルケアの状況に直面しており、職業生活と家庭生活の両立が極めて困難になっています。具体的には、以下のような複合的負担が生じています。
- 朝の保育園送迎と、親の通院付き添いが同日に発生し、出勤や業務開始時間に影響する
- 介護と育児のダブルの夜間対応による慢性的な睡眠不足と疲労
- 子どもの学校行事や病児対応に加え、親の緊急入院など、突発的な予定変更への対応負荷
- 精神的な張り詰めと自己犠牲によるメンタル不調のリスク増大
また、ダブルケアを担う従業員は、 次のようなキャリア面での制約やあきらめも経験しています。
- 昇進や異動のチャンスを断念する
- 時短勤務や在宅勤務への切り替えによる業務幅の限定
- 責任あるプロジェクトから外れる、または希望しない職務への配置転換
こうした背景から、ダブルケア層への配慮は、キャリア継続支援や働きがいの確保という観点でも企業にとって重要な人的資本投資といえます。
経済産業省の位置づけと対応推奨
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(2024年)では、両立支援は次のように定義されています。「両立支援は、人的資本の損失を防ぎ、企業の持続可能性を高める戦略的経営課題である」
推奨される対応
トップの支援姿勢の明確化:企業トップが両立支援の必要性を明言し、組織全体に明確なメッセージとして発信することで、従業員の制度利用に対する心理的ハードルを下げ、社内文化の醸成にもつながります。
- 制度設計と“使える環境”の整備:制度が形だけのものにならないよう、実際のニーズに合った柔軟かつ実効性ある仕組みを設計し、誰もが気兼ねなく利用できる風土と運用体制を整える必要があります。
- 管理職教育と現場対応力の強化:部下の状況に気づき、早期に適切な支援策を講じられるよう、管理職に対して介護支援や制度運用に関する実践的な教育を行うことが欠かせません。
- 実態把握と早期支援の仕組みづくり:従業員の介護や育児の状況を把握し、困難を抱える前に支援が提供できるよう、サーベイや面談、相談窓口の設置などを通じた早期介入体制を構築します。
両立支援がもたらす経営的価値
離職防止・人的資本の維持と活用:介護や育児を理由に優秀な人材が離職することを防ぎ、企業にとっての人的資源を継続的に活用することで、生産性と知的資本の損失を抑制します。
- 従業員の安心感とエンゲージメント向上:生活上の困難に対して会社からの支援があるという安心感が、従業員の職場への信頼や帰属意識を高め、意欲的に働くことにつながります。
- 多様性と包摂性ある職場文化の形成:介護・育児を担う従業員も活躍できる環境づくりは、多様な背景を持つ人材が協働できる職場文化を育み、イノベーションと持続性を強化します。